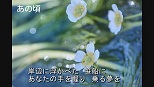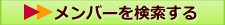バラクロフ さんの日記
2025
10月
10
(金)
20:44
本文
かつて日本のお葬式といえば、親族・友人・地域社会が一堂に会する大規模な儀式が一般的でした。しかし近年はその姿が大きく変わりつつあります。
特に注目されるのが、「家族葬」や「直葬(ちょくそう)」 です。
家族葬:近親者やごく限られた人だけで行う小規模な葬儀。会葬者は数名から十数名程度にとどまり、儀式の負担を軽減できる。
直葬:通夜や告別式を行わず、火葬のみを行うシンプルな形式。費用は数十万円以下に抑えられる場合もあり、都市部を中心に急増。
背景には、少子高齢化・核家族化・経済的事情・宗教離れといった複合的な要因があります。かつての「立派なお葬式=親孝行」という価値観が薄れ、「最後はシンプルに、負担をかけないで送りたい」 という声が増えているのです。
葬儀屋の闇──見積もりの不透明さと“悲しみビジネス”
しかし、この「多様化」の陰には、業界特有の闇も潜んでいます。
1. 不透明な料金体系
葬儀の費用は全国平均で約120〜150万円と言われていますが、その内訳は非常に不透明です。
例えば「祭壇一式」「お別れプラン」などの曖昧な名目で高額請求されることも少なくありません。実際に、葬儀後に「こんなにかかるとは思わなかった」とトラブルになるケースは後を絶ちません。
2. 弱みに付け込む商法
遺族は突然の死に直面し、冷静な判断ができない状態にあります。その心理に付け込み、「このランク以上の棺でないと失礼です」「花を追加した方がよろしいですよ」 といった営業トークで、次々と追加費用を積み上げる業者も存在します。
3. “紹介料ビジネス”の実態
病院や介護施設から紹介される葬儀社の多くは、裏で「紹介料」を支払っています。この費用が結局は葬儀代に上乗せされ、遺族が負担しているのです。つまり、紹介の安心感が必ずしも“良心的”につながるとは限りません。
お葬式のこれから──「送る人」と「送られる人」の本音
近年の調査では、6割以上の高齢者が「できるだけ簡素な葬儀でいい」と考えている というデータもあります。豪華な祭壇や長時間の儀式ではなく、「自分らしく」「静かに」「家族だけで」 という形が求められているのです。
一方で、葬儀をビジネスとする業者にとっては、簡素化は収益減に直結します。だからこそ業界は“プランの複雑化”や“高額オプション”を仕掛けてくる。ここにこそ「葬儀屋の闇」があると言えるでしょう。
まとめ──「死の準備」はタブーではない
日本では「死を語るのは縁起でもない」とされがちですが、むしろ生前から自分の希望を伝えておくことこそ大切です。
エンディングノートを活用し、家族葬・直葬・無宗教葬など、自分が望む形をあらかじめ決めておけば、葬儀業者に振り回されるリスクも減らせます。
お葬式の多様化は「誰のための葬儀か?」という問いを私たちに投げかけています。亡くなる人の尊厳と、残された人の負担。その両方を見据えて、私たちはもっと賢く選び取っていく必要があるのです。
「明日は我が身──その覚悟を、私たちは持たねばならない。」
特に注目されるのが、「家族葬」や「直葬(ちょくそう)」 です。
家族葬:近親者やごく限られた人だけで行う小規模な葬儀。会葬者は数名から十数名程度にとどまり、儀式の負担を軽減できる。
直葬:通夜や告別式を行わず、火葬のみを行うシンプルな形式。費用は数十万円以下に抑えられる場合もあり、都市部を中心に急増。
背景には、少子高齢化・核家族化・経済的事情・宗教離れといった複合的な要因があります。かつての「立派なお葬式=親孝行」という価値観が薄れ、「最後はシンプルに、負担をかけないで送りたい」 という声が増えているのです。
葬儀屋の闇──見積もりの不透明さと“悲しみビジネス”
しかし、この「多様化」の陰には、業界特有の闇も潜んでいます。
1. 不透明な料金体系
葬儀の費用は全国平均で約120〜150万円と言われていますが、その内訳は非常に不透明です。
例えば「祭壇一式」「お別れプラン」などの曖昧な名目で高額請求されることも少なくありません。実際に、葬儀後に「こんなにかかるとは思わなかった」とトラブルになるケースは後を絶ちません。
2. 弱みに付け込む商法
遺族は突然の死に直面し、冷静な判断ができない状態にあります。その心理に付け込み、「このランク以上の棺でないと失礼です」「花を追加した方がよろしいですよ」 といった営業トークで、次々と追加費用を積み上げる業者も存在します。
3. “紹介料ビジネス”の実態
病院や介護施設から紹介される葬儀社の多くは、裏で「紹介料」を支払っています。この費用が結局は葬儀代に上乗せされ、遺族が負担しているのです。つまり、紹介の安心感が必ずしも“良心的”につながるとは限りません。
お葬式のこれから──「送る人」と「送られる人」の本音
近年の調査では、6割以上の高齢者が「できるだけ簡素な葬儀でいい」と考えている というデータもあります。豪華な祭壇や長時間の儀式ではなく、「自分らしく」「静かに」「家族だけで」 という形が求められているのです。
一方で、葬儀をビジネスとする業者にとっては、簡素化は収益減に直結します。だからこそ業界は“プランの複雑化”や“高額オプション”を仕掛けてくる。ここにこそ「葬儀屋の闇」があると言えるでしょう。
まとめ──「死の準備」はタブーではない
日本では「死を語るのは縁起でもない」とされがちですが、むしろ生前から自分の希望を伝えておくことこそ大切です。
エンディングノートを活用し、家族葬・直葬・無宗教葬など、自分が望む形をあらかじめ決めておけば、葬儀業者に振り回されるリスクも減らせます。
お葬式の多様化は「誰のための葬儀か?」という問いを私たちに投げかけています。亡くなる人の尊厳と、残された人の負担。その両方を見据えて、私たちはもっと賢く選び取っていく必要があるのです。
「明日は我が身──その覚悟を、私たちは持たねばならない。」
閲覧(293)
| カテゴリー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
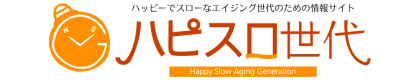





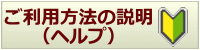
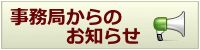

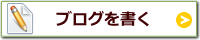
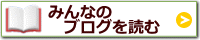
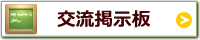
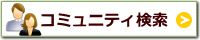
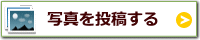
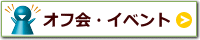
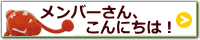
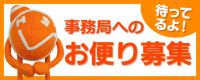
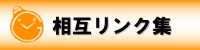


 前の日記
前の日記