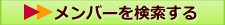津覇 さんの日記
2025
6月
6
(金)
23:02
本文
私たちが人生の中で経験する感情の中でも、「憎しみ」は特に強く、持続的で、時には自分自身をも傷つける力を持っています。心理学の視点から見ると、憎しみとは単なる怒りの延長ではなく、自己を守るために働く深い心理的メカニズムが関与した感情です。憎しみはしばしば恐れや不安、そして過去の傷つき体験から生まれます。人は自己の価値や安全が脅かされると、本能的に「敵」を認識し、その対象に強い否定的感情を向けます。このとき脳は、合理的な判断よりも感情を優先し、自分の中の受け入れがたい部分を他者に投影することさえあります。
また、心理学では「集団同一性理論」によって、憎しみが個人を超えて社会現象にまで拡大することも説明されます。人は自分の所属する集団(内集団)を守ろうとするあまり、他の集団(外集団)を「異物」として排除しようとする傾向があります。これが偏見や差別、そしてヘイトスピーチといった社会問題の根底にあるのです。
憎しみは人間関係を壊し、心身の健康に悪影響を与えるだけでなく、暴力や報復といった深刻な行動にもつながりかねません。しかし心理学は、私たちがこの感情にどう向き合い、解放されるかの方法も教えてくれます。まず大切なのは、自分の中にある憎しみの感情に「気づく」ことです。それを否定せず、静かに見つめることで、私たちはその背後にある不安や痛みを理解し始めます。そして、相手の立場や背景に思いを馳せる「共感」、出来事の意味を新たな視点から見直す「リフレーミング」、そして最終的には「許し」——それは相手のためではなく、自分の心の平穏のために——が、心の自由を取り戻す鍵となるのです。
憎しみを持つことは決して「悪」ではありません。それは私たちが傷ついた証でもあり、真剣に生きてきた証拠でもあります。ただし、その感情に支配されるのではなく、心理学という光を通して理解し、自分の力で手放していくことこそが、真の心の強さと言えるでしょう。
また、心理学では「集団同一性理論」によって、憎しみが個人を超えて社会現象にまで拡大することも説明されます。人は自分の所属する集団(内集団)を守ろうとするあまり、他の集団(外集団)を「異物」として排除しようとする傾向があります。これが偏見や差別、そしてヘイトスピーチといった社会問題の根底にあるのです。
憎しみは人間関係を壊し、心身の健康に悪影響を与えるだけでなく、暴力や報復といった深刻な行動にもつながりかねません。しかし心理学は、私たちがこの感情にどう向き合い、解放されるかの方法も教えてくれます。まず大切なのは、自分の中にある憎しみの感情に「気づく」ことです。それを否定せず、静かに見つめることで、私たちはその背後にある不安や痛みを理解し始めます。そして、相手の立場や背景に思いを馳せる「共感」、出来事の意味を新たな視点から見直す「リフレーミング」、そして最終的には「許し」——それは相手のためではなく、自分の心の平穏のために——が、心の自由を取り戻す鍵となるのです。
憎しみを持つことは決して「悪」ではありません。それは私たちが傷ついた証でもあり、真剣に生きてきた証拠でもあります。ただし、その感情に支配されるのではなく、心理学という光を通して理解し、自分の力で手放していくことこそが、真の心の強さと言えるでしょう。
閲覧(442)
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
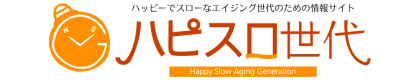
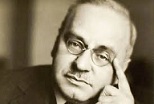




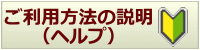
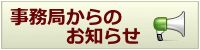

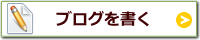
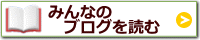
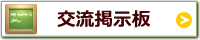
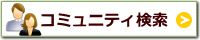
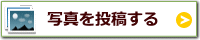
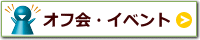
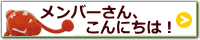
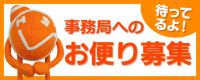
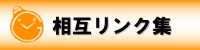


 前の日記
前の日記