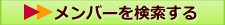tinc さんの日記
2021
6月
18
(金)
21:14
本文
在宅で事務業務に従事している現在もビデオ通話を介したり時には職場やその周辺へ出向いていったりして同僚と会話をする機会は多い。内容は単純な事務連絡から職場の運営方針に関わることまで様々である。今日はある先輩との個人的な雑談が長引いた。先輩の話は当初は音楽の嗜好や日常生活における小さな拘りの数々という和やかなものであったのが、継続するにつれて次第に先輩自身の抱える家庭環境や経済事情といったことに係る具体的な問題のいくつかが顔を出し、それらに由来する先輩の深い懊悩と苦悶を描写するものへと発展していった。
私はただ平坦な相槌を打ちながらそれを聞いていた。内心では何か言ったほうがよいのかとも思っていたし、具体的な助言と呼べるようなものも幾ばくかは頭の中を訪れたものの、無い頭であれこれ考えた結果私は沈黙に近い態度を貫いた。
誰かが自身の抱える問題について私へ話す時、私という人間はその問題のほうに着目しがちである。そしてその問題への解決策を提案したり、時には私として可能な援助について申し出たりする。
しかしこの時、私は重大な二つの前提を見失っている。一つはその人は問題の当事者であるが故に誰よりもその問題に向き合い続けてきたのであり、私の思いつくような解決策を既に考慮した末に何らかの理由で採用しなかったのであろうということ。もう一つは私へ自身の内面について打ち明けざるを得ないところまで追い込まれているような人は、具体的な解決策を実行する力も、私の援助を受け入れるべきかを判断する力も、その状況で自身がどうしたいのかを考える力すらも、おそらく最早失ってしまっているであろうということ。
苦しくてたまらずようやく私へ心中を吐露するという人は既に枯渇している。その状態の人へ何かをせよとか何かをするなと言うのは無理な話である。枯渇した人間は希望も意志も力も持たない。ただまだ死んでいないというだけである。
今日の私は先輩の話を聞いて重苦しく感じつつ、安直な助言や援助の申し出には堕するまいと注意した。先輩に問題があるとすればそれは家庭環境や経済事情というものよりも、それらに追い詰められ私などへ打ち明けるところへ至るまで他の誰かの援助を求められなかった孤独ではないかと思った。先輩は自身を苦しめる問題について私へ話している。しかし私はそれらの問題に立ち向かうよりも先に、問題に苦しむ先輩という人の姿を見つめなければならない。
話の最後に先輩は「すみません、つまらないことを言ってしまって」と呟いた。私は今日聞いた問題については具体的な解決策を考えてみると伝えた上で、「また気が向いたら聞かせてください」と述べて通話を終えた。
もし私の想像の通り先輩の問題の根本が孤独であるならば、先輩には孤独でなくなって頂きたいところである。孤独な人間は多くの災厄に見舞われる。孤独でない人が他人の助力を得ながら解決する問題に一人で立ち向かわねばならないことから常に消耗しているし、徒党を組んだ悪人の搾取の標的になりやすい。そして自身を孤独だと感じている人は、他人の助力を得ることに不信感や罪悪感を抱くことから孤独を脱する術を持たないことも多い。
業務を終えた今も私は先輩のことや孤独というものについてあれこれと考えている。
私の想像が外れていて、先輩がさほど孤独でないならばそれはそれでよい。問題は早期に解決に向かうであろう。
しかし実際に私の云う孤独が問題の本質的な部分を形成するならば、ある程度長い目で見て腰を据えてかかる必要がある。「孤独ではない」という感覚が当事者の内部に根を張るまでは、仮に現在ある問題の解決に成功しても次の問題がまた重大化することを繰り返すことになる。
私は自身のできる範囲で先輩に寄り添おうと思う。
誰もが問題を抱えているが、そこに在るのは「人に付随した問題」ではなく「問題を抱えた人」である。
私などが簡単にああしろこうしろと言って済むような話ばかりで世の中ができているなら、誰も苦労しないし誰も幸せでないし、世の中そのものがとうの昔に無くなっているであろう。
私はただ平坦な相槌を打ちながらそれを聞いていた。内心では何か言ったほうがよいのかとも思っていたし、具体的な助言と呼べるようなものも幾ばくかは頭の中を訪れたものの、無い頭であれこれ考えた結果私は沈黙に近い態度を貫いた。
誰かが自身の抱える問題について私へ話す時、私という人間はその問題のほうに着目しがちである。そしてその問題への解決策を提案したり、時には私として可能な援助について申し出たりする。
しかしこの時、私は重大な二つの前提を見失っている。一つはその人は問題の当事者であるが故に誰よりもその問題に向き合い続けてきたのであり、私の思いつくような解決策を既に考慮した末に何らかの理由で採用しなかったのであろうということ。もう一つは私へ自身の内面について打ち明けざるを得ないところまで追い込まれているような人は、具体的な解決策を実行する力も、私の援助を受け入れるべきかを判断する力も、その状況で自身がどうしたいのかを考える力すらも、おそらく最早失ってしまっているであろうということ。
苦しくてたまらずようやく私へ心中を吐露するという人は既に枯渇している。その状態の人へ何かをせよとか何かをするなと言うのは無理な話である。枯渇した人間は希望も意志も力も持たない。ただまだ死んでいないというだけである。
今日の私は先輩の話を聞いて重苦しく感じつつ、安直な助言や援助の申し出には堕するまいと注意した。先輩に問題があるとすればそれは家庭環境や経済事情というものよりも、それらに追い詰められ私などへ打ち明けるところへ至るまで他の誰かの援助を求められなかった孤独ではないかと思った。先輩は自身を苦しめる問題について私へ話している。しかし私はそれらの問題に立ち向かうよりも先に、問題に苦しむ先輩という人の姿を見つめなければならない。
話の最後に先輩は「すみません、つまらないことを言ってしまって」と呟いた。私は今日聞いた問題については具体的な解決策を考えてみると伝えた上で、「また気が向いたら聞かせてください」と述べて通話を終えた。
もし私の想像の通り先輩の問題の根本が孤独であるならば、先輩には孤独でなくなって頂きたいところである。孤独な人間は多くの災厄に見舞われる。孤独でない人が他人の助力を得ながら解決する問題に一人で立ち向かわねばならないことから常に消耗しているし、徒党を組んだ悪人の搾取の標的になりやすい。そして自身を孤独だと感じている人は、他人の助力を得ることに不信感や罪悪感を抱くことから孤独を脱する術を持たないことも多い。
業務を終えた今も私は先輩のことや孤独というものについてあれこれと考えている。
私の想像が外れていて、先輩がさほど孤独でないならばそれはそれでよい。問題は早期に解決に向かうであろう。
しかし実際に私の云う孤独が問題の本質的な部分を形成するならば、ある程度長い目で見て腰を据えてかかる必要がある。「孤独ではない」という感覚が当事者の内部に根を張るまでは、仮に現在ある問題の解決に成功しても次の問題がまた重大化することを繰り返すことになる。
私は自身のできる範囲で先輩に寄り添おうと思う。
誰もが問題を抱えているが、そこに在るのは「人に付随した問題」ではなく「問題を抱えた人」である。
私などが簡単にああしろこうしろと言って済むような話ばかりで世の中ができているなら、誰も苦労しないし誰も幸せでないし、世の中そのものがとうの昔に無くなっているであろう。
閲覧(2267)
| カテゴリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
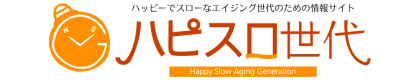
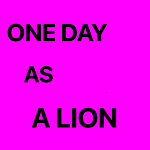




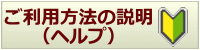
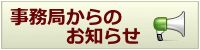

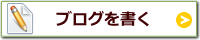
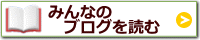
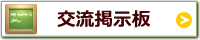
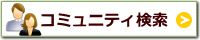
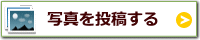
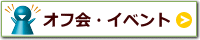
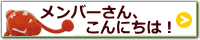
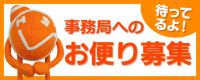
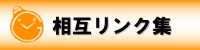


 前の日記
前の日記