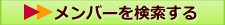ひろひろ48 さんの日記
2021
6月
6
(日)
21:11
本文
介護ホームで、週2日で、バイトしています。
人間、年取ると、あちこちガタが来ます。そういう自分も50代では50肩になったり、60代初めには虚血性心筋症になったり、60代半ばで前立腺がんになったり、なんとか治療は終えておりますが、ここ数年は、坐骨神経痛で足がときどき痛くなります。歌をはじめ、まだまだやりたいことはあるので、メンタルには大丈夫です。
介護ホームでは、100歳の方はもうめずらしくありません。車いすの方もおられますが、しっかりご自分の足で歩かれてる方も多いです。個人差が大きいですね。
認知症の方も多く入居されています。入居間もないころは、普通の人とあまり変わりはありません。でも、1年2年すると進行してきて、数年すると運動機能も低下して、あまり動けなくなります。
認知症の予防は、軽度認知症障害(MCI)での早期発見で、回復か発症を遅らせることができます。発症してもフランスで考えられたユマニチュード(フランス語で「人間らしさ」という意味)で進行を遅らせる可能性もあります。治療薬は動物実験ではいい結果を得たものが、人への治験では、ことごとくだめで、絶望しされていますが、とうのは、脳は、極めて強固な免疫防御がされていて薬剤が届きにくいのです。
いつか、いい治療法が見つかるかもしれませんが、それまでは、支えながら生きるしかありません。それには、認知症になった人が、なにをどう考えているかを知ることが大切です。土曜の夕刊の記事「土曜訪問」から参考になれば:
病気理解する一助に: 認知症の義母の視点で日常つづった「全員悪人」を出版: 村井理子さん(翻訳家・エッセイスト)
<知らない女が毎日家にやってくる。ずかずかと玄関から上がり込んで、大きな声で挨拶(あいさつ)をしたかと思ったら、勝手にキッチンに入っていく>
翻訳家でエッセイストの村井理子さん(50)が一風変わった本『全員悪人』(CCCメディアハウス)を出した。第一章の冒頭は、さながらホラー小説のよう。だが読み進めれば、状況がのみ込める。始まりから終わりまで、認知症を発症した八十代の義母から見た日常が書かれているのだ。
「書くかは迷いました。本人も読めば分かるでしょうし。でも今までも生活周りを書くことが多くて、(介護は)一番時間を割いていることでもあるので、これかな、と」。緊急事態宣言下のため、取材はオンライン。つないだ滋賀県の自宅は、琵琶湖まで走れば二分ほどで着く場所にある。「こちらは曇りで、湖面が白く見えます」と朗らかな声で返す村井さんは、夫と中学三年になる双子の息子、愛犬と暮らす。車で十分先に住む義母に異変を感じたのは三、四年前だった。
ある日のお土産が三割引きのつぶれたコロッケ。何でもないことだが、義母はいつも一番良い物を選んで持ってきてくれる人だった。だからこそ「妙な違和感があった」。症状は「顔のしわが濃くなるように」少しずつ進み、義父をたたいたり、浮気を疑ったり。お金が取られたと言うこともあった。途方に暮れ、けんかになったが、ある一件で見方が変わったという。
「義母が窓の外を指して『誰々さんが歩いてる』って言うんです。でも誰もいない。ああ、本人には確実に見えていて絶対的な真実なんだなと。これは戸惑うと思いました」。じっくり話を聞くと、荒唐無稽に思えた行為にも理由があった。夫がロボットの<パパゴン>にすり替わって憎くなったこと、家計簿の計算が合わず、出入りするヘルパーを疑ったこと。浮気妄想が出るのは「大好きな人を攻撃してしまう病」ゆえと知り、義母が夫の入院中には毎日見舞っていた姿を思い出した。
義母の視点で“実話”を書くと「認知症やお義母(かあ)さんを、ずいぶん理解できた」。後書きには、認知症患者が抱く<変化への恐れや苦しみ、孤立、それに伴う焦燥感>に思いをはせ<一番の味方であり続けたい>と記した。「介護は悲しみ一色じゃない。本が行動を理解する、ちょっとしたきっかけになれば」と願う。
静岡県焼津市生まれ。家族そろって本好きで、小学生のころには母親の本棚にあった渡辺淳一さんや五木寛之さんらの小説を読んだ。カナダで過ごした高校時代も、京都外国語大に進んだ後も、読書は身近。そこで養われた読解力と空想力は、翻訳家として活躍する素地となった。
デビューのきっかけは、趣味でウェブ上に公開していたブッシュ米大統領の発言集。出版社の目に留まり、二〇〇三年に『ブッシュ妄言録』として刊行。以降『ローラ・ブッシュ自伝』など、ノンフィクションを中心に二十冊ほどの翻訳を手掛けてきた。
黒子に徹して訳すうち、「自分の話を書きたい」と一六年からは雑誌やウェブマガジンなどで連載を開始。「キラキラな生活というより、ダラダラ」と笑うが、愛犬との日々を記した『犬(きみ)がいるから』、子育てを中心にした『村井さんちの生活』など、出すエッセーは好評を得てきた。
中でも昨年刊行の『兄の終(しま)い』は、八刷三万八千部と静かな反響を読んだ。絶縁状態にあった兄が遠い地で遺体で見つかり、弔いに向き合った五日間を記す。「置かれた状況が受け入れられず、しんどくって。書くことで消化していく、というのがありましたね」
認知症に子育て、きょうだいの確執…。一見避けたくなるような題材も、村井さんは「羞恥心はない」という。書くのは「読む人の反応があるから。その喜びが大きい」と軽やかに言い切る。次作で書きたいのは、疎遠なまま亡くなった両親のこと。「まだ理解できないんですよね。どんな人たちだったのか、自分も親になって興味が湧いた」。これからも、ありのままを、飾らない文章でつづっていく。 (世古紘子)
人間、年取ると、あちこちガタが来ます。そういう自分も50代では50肩になったり、60代初めには虚血性心筋症になったり、60代半ばで前立腺がんになったり、なんとか治療は終えておりますが、ここ数年は、坐骨神経痛で足がときどき痛くなります。歌をはじめ、まだまだやりたいことはあるので、メンタルには大丈夫です。
介護ホームでは、100歳の方はもうめずらしくありません。車いすの方もおられますが、しっかりご自分の足で歩かれてる方も多いです。個人差が大きいですね。
認知症の方も多く入居されています。入居間もないころは、普通の人とあまり変わりはありません。でも、1年2年すると進行してきて、数年すると運動機能も低下して、あまり動けなくなります。
認知症の予防は、軽度認知症障害(MCI)での早期発見で、回復か発症を遅らせることができます。発症してもフランスで考えられたユマニチュード(フランス語で「人間らしさ」という意味)で進行を遅らせる可能性もあります。治療薬は動物実験ではいい結果を得たものが、人への治験では、ことごとくだめで、絶望しされていますが、とうのは、脳は、極めて強固な免疫防御がされていて薬剤が届きにくいのです。
いつか、いい治療法が見つかるかもしれませんが、それまでは、支えながら生きるしかありません。それには、認知症になった人が、なにをどう考えているかを知ることが大切です。土曜の夕刊の記事「土曜訪問」から参考になれば:
病気理解する一助に: 認知症の義母の視点で日常つづった「全員悪人」を出版: 村井理子さん(翻訳家・エッセイスト)
<知らない女が毎日家にやってくる。ずかずかと玄関から上がり込んで、大きな声で挨拶(あいさつ)をしたかと思ったら、勝手にキッチンに入っていく>
翻訳家でエッセイストの村井理子さん(50)が一風変わった本『全員悪人』(CCCメディアハウス)を出した。第一章の冒頭は、さながらホラー小説のよう。だが読み進めれば、状況がのみ込める。始まりから終わりまで、認知症を発症した八十代の義母から見た日常が書かれているのだ。
「書くかは迷いました。本人も読めば分かるでしょうし。でも今までも生活周りを書くことが多くて、(介護は)一番時間を割いていることでもあるので、これかな、と」。緊急事態宣言下のため、取材はオンライン。つないだ滋賀県の自宅は、琵琶湖まで走れば二分ほどで着く場所にある。「こちらは曇りで、湖面が白く見えます」と朗らかな声で返す村井さんは、夫と中学三年になる双子の息子、愛犬と暮らす。車で十分先に住む義母に異変を感じたのは三、四年前だった。
ある日のお土産が三割引きのつぶれたコロッケ。何でもないことだが、義母はいつも一番良い物を選んで持ってきてくれる人だった。だからこそ「妙な違和感があった」。症状は「顔のしわが濃くなるように」少しずつ進み、義父をたたいたり、浮気を疑ったり。お金が取られたと言うこともあった。途方に暮れ、けんかになったが、ある一件で見方が変わったという。
「義母が窓の外を指して『誰々さんが歩いてる』って言うんです。でも誰もいない。ああ、本人には確実に見えていて絶対的な真実なんだなと。これは戸惑うと思いました」。じっくり話を聞くと、荒唐無稽に思えた行為にも理由があった。夫がロボットの<パパゴン>にすり替わって憎くなったこと、家計簿の計算が合わず、出入りするヘルパーを疑ったこと。浮気妄想が出るのは「大好きな人を攻撃してしまう病」ゆえと知り、義母が夫の入院中には毎日見舞っていた姿を思い出した。
義母の視点で“実話”を書くと「認知症やお義母(かあ)さんを、ずいぶん理解できた」。後書きには、認知症患者が抱く<変化への恐れや苦しみ、孤立、それに伴う焦燥感>に思いをはせ<一番の味方であり続けたい>と記した。「介護は悲しみ一色じゃない。本が行動を理解する、ちょっとしたきっかけになれば」と願う。
静岡県焼津市生まれ。家族そろって本好きで、小学生のころには母親の本棚にあった渡辺淳一さんや五木寛之さんらの小説を読んだ。カナダで過ごした高校時代も、京都外国語大に進んだ後も、読書は身近。そこで養われた読解力と空想力は、翻訳家として活躍する素地となった。
デビューのきっかけは、趣味でウェブ上に公開していたブッシュ米大統領の発言集。出版社の目に留まり、二〇〇三年に『ブッシュ妄言録』として刊行。以降『ローラ・ブッシュ自伝』など、ノンフィクションを中心に二十冊ほどの翻訳を手掛けてきた。
黒子に徹して訳すうち、「自分の話を書きたい」と一六年からは雑誌やウェブマガジンなどで連載を開始。「キラキラな生活というより、ダラダラ」と笑うが、愛犬との日々を記した『犬(きみ)がいるから』、子育てを中心にした『村井さんちの生活』など、出すエッセーは好評を得てきた。
中でも昨年刊行の『兄の終(しま)い』は、八刷三万八千部と静かな反響を読んだ。絶縁状態にあった兄が遠い地で遺体で見つかり、弔いに向き合った五日間を記す。「置かれた状況が受け入れられず、しんどくって。書くことで消化していく、というのがありましたね」
認知症に子育て、きょうだいの確執…。一見避けたくなるような題材も、村井さんは「羞恥心はない」という。書くのは「読む人の反応があるから。その喜びが大きい」と軽やかに言い切る。次作で書きたいのは、疎遠なまま亡くなった両親のこと。「まだ理解できないんですよね。どんな人たちだったのか、自分も親になって興味が湧いた」。これからも、ありのままを、飾らない文章でつづっていく。 (世古紘子)
閲覧(3238)
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |






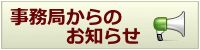

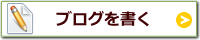
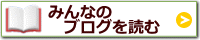
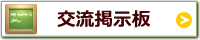
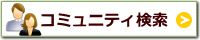
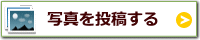
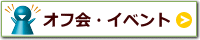
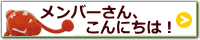




 前の日記
前の日記