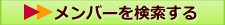tinc さんの日記
2021
3月
10
(水)
22:46
本文
ある福祉施設の夜勤のパートを開始して2週間ほどになる。福祉施設の運営団体は社会福祉士等福祉の関連法令や制度に熟達した人々でその中核が構成されることが多数であるが、私の現在の勤務先では理事長をはじめとする数名の心理師資格を有する職員によって組織運営や現場業務の方向性が決定されている。心理師は心療内科におけるカウンセリング等医療職の印象が世間において強い一方で、患者の知的能力や生育歴の検査および評価等、対応する領域から福祉分野への親和性も高く、少数派とあれど無理のある構成ではない。私が見るに上長や先輩職員たちはいずれも高い見識と誠実な熱意を持って施設利用者の支援に臨んでおり、単に有能なだけではない、福祉従事者として高水準の人員が揃っている。
夜勤職員の私の業務は緊急時の対応に備えた待機が大半を占め、その合間に日勤や夕勤の職員の対応しきれない雑務を処理している。警察や救急への通報を行う類の事態が発生した場合に一人である程度の現場判断を行い対応することにはかなりの負荷を感じるとはいえ、事後処理や事態を受けての方策決定は権限と責任を持つ上長たちが行うので、私は大きな社会的責任を追求されること無く経験を積むことのできるある意味で気楽な立場にあると云える。
とはいえいつまでも貧弱な夜警のような業務ばかりしているわけにもゆかず、私もいずれは相談援助等の直接の利用者支援を自身の業務の本体とせざるを得ない。
私は現在上長や先輩職員の利用者対応やその記録文書を観察しそれらをトレースすることを試みている。利用者の信頼を得て彼らへの支援行為を行う許しを得るには、どのような表情や身のこなしや言葉選びを表出し、彼らの話を聞くにどのような相槌を打てばよいか。時に話の合間に小さな助言を挿入しているように見えるが、その助言の内容はどの程度なら本人へ努力を要求するものであってよいのか。記録文書に示唆される、職員が利用者のどの部分に着目してそこから何を推測し、利用者本人の目標達成という結果を得るためにどのような手法を候補に挙げているかということ。その他税金を投入して行われる事業としての健全性を担保するために堅持されねばならない成果の達成と利用者本人の意向尊重を両立するために必要な計画立案の感覚等。背後には職員それぞれのまた団体としての人間観や社会観が存在するはずで、私はそれを掴み取り理解するために周囲の人々の模倣を重ねているところである。せっかく福祉施設に勤務しているのに利用者よりも職員を注視しなければならないということで仕事の本質から少し離れてしまうものの、職員として違和感の無い自己像をアピールすることでやがて利用者からも何事かを話されるようになるものと思う。挨拶回りみたいな段階であるのかもしれない。
社会保障は今後も弱体化の一途を辿ることが予想され、福祉事業に従事して生計を立てることは過酷になるばかりであろう。それでも私が福祉業を面白く思い今後も続けてゆくことを望むのは、それが社会の全体を対象に思考し、相反する立場の人々の間に立って折衝の途を探ることを許す仕事であるからである。また自身の持つ限りの知識と知恵を動員してひとと接することを日々の業務とする中で、時に思わぬ在り方で自分の考えや記憶が役に立つことがあるという驚きがあるからでもある。
弱者の権利がいかにして擁護されるべきかということは、それを考えること自体が一つの悪と見なされることも少なくない。ずっとそうだったしこれからもそうだろう。しかし福祉を志す人々はその中で苦闘を続けつつ自らの倫理観に洗練を重ねてきたのであり、当初は温情主義的な意識に根差す救済の試みであった福祉活動は現在では共生と相互扶助という本来あるべき自由で平等な社会の実現を志向するものに変化している。
私は我が身を振り返る。私は過去から現在に至るまでの自分を否定しない。できなかったことは仕方がないし今の自分をそれほど嫌いではない。つまり今の私にも知らないことやできないことが山ほどありそれゆえに他者の権利を害うこともある。そのままでいるのはやはり自分として好ましいと思えないので、私は私のために今とは違う私になることを望むのである。
「コピーキャット」は「模倣犯」という意味である。先輩たちのコピーキャットである今の私は世間からの非難にさらされがちな福祉分野において活動し、新しい自分になるための材料をたらふく貪っていると感じる。猫が9つの命を持つと云うが如く、いつもタフにしなやかにありたいものである。
夜勤職員の私の業務は緊急時の対応に備えた待機が大半を占め、その合間に日勤や夕勤の職員の対応しきれない雑務を処理している。警察や救急への通報を行う類の事態が発生した場合に一人である程度の現場判断を行い対応することにはかなりの負荷を感じるとはいえ、事後処理や事態を受けての方策決定は権限と責任を持つ上長たちが行うので、私は大きな社会的責任を追求されること無く経験を積むことのできるある意味で気楽な立場にあると云える。
とはいえいつまでも貧弱な夜警のような業務ばかりしているわけにもゆかず、私もいずれは相談援助等の直接の利用者支援を自身の業務の本体とせざるを得ない。
私は現在上長や先輩職員の利用者対応やその記録文書を観察しそれらをトレースすることを試みている。利用者の信頼を得て彼らへの支援行為を行う許しを得るには、どのような表情や身のこなしや言葉選びを表出し、彼らの話を聞くにどのような相槌を打てばよいか。時に話の合間に小さな助言を挿入しているように見えるが、その助言の内容はどの程度なら本人へ努力を要求するものであってよいのか。記録文書に示唆される、職員が利用者のどの部分に着目してそこから何を推測し、利用者本人の目標達成という結果を得るためにどのような手法を候補に挙げているかということ。その他税金を投入して行われる事業としての健全性を担保するために堅持されねばならない成果の達成と利用者本人の意向尊重を両立するために必要な計画立案の感覚等。背後には職員それぞれのまた団体としての人間観や社会観が存在するはずで、私はそれを掴み取り理解するために周囲の人々の模倣を重ねているところである。せっかく福祉施設に勤務しているのに利用者よりも職員を注視しなければならないということで仕事の本質から少し離れてしまうものの、職員として違和感の無い自己像をアピールすることでやがて利用者からも何事かを話されるようになるものと思う。挨拶回りみたいな段階であるのかもしれない。
社会保障は今後も弱体化の一途を辿ることが予想され、福祉事業に従事して生計を立てることは過酷になるばかりであろう。それでも私が福祉業を面白く思い今後も続けてゆくことを望むのは、それが社会の全体を対象に思考し、相反する立場の人々の間に立って折衝の途を探ることを許す仕事であるからである。また自身の持つ限りの知識と知恵を動員してひとと接することを日々の業務とする中で、時に思わぬ在り方で自分の考えや記憶が役に立つことがあるという驚きがあるからでもある。
弱者の権利がいかにして擁護されるべきかということは、それを考えること自体が一つの悪と見なされることも少なくない。ずっとそうだったしこれからもそうだろう。しかし福祉を志す人々はその中で苦闘を続けつつ自らの倫理観に洗練を重ねてきたのであり、当初は温情主義的な意識に根差す救済の試みであった福祉活動は現在では共生と相互扶助という本来あるべき自由で平等な社会の実現を志向するものに変化している。
私は我が身を振り返る。私は過去から現在に至るまでの自分を否定しない。できなかったことは仕方がないし今の自分をそれほど嫌いではない。つまり今の私にも知らないことやできないことが山ほどありそれゆえに他者の権利を害うこともある。そのままでいるのはやはり自分として好ましいと思えないので、私は私のために今とは違う私になることを望むのである。
「コピーキャット」は「模倣犯」という意味である。先輩たちのコピーキャットである今の私は世間からの非難にさらされがちな福祉分野において活動し、新しい自分になるための材料をたらふく貪っていると感じる。猫が9つの命を持つと云うが如く、いつもタフにしなやかにありたいものである。
閲覧(2349)
| カテゴリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
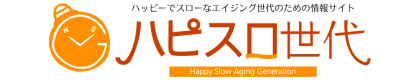
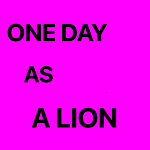




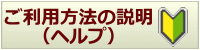
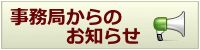

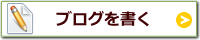
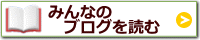
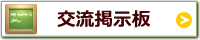
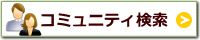
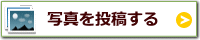
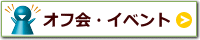
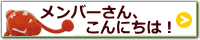
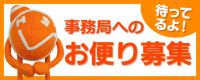
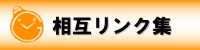


 前の日記
前の日記