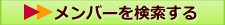ひろひろ48 さんの日記
2021
1月
27
(水)
21:20
本文
昨年10月に緊急出版された「私たちはどういきるか」から別のメッセージから。日本でのコロナ、第3波で緊急事態宣言で、すこし感染者数が減ってきたのもあるけど、ヨーロッパの危機感とはかなり差がある。第一波で、1-2か月で、数万人が亡くなる状況、ドイツの人口やく8000万人、ほかの国も6000万人で、ひと月で約一万人は亡くなれば、ロックダウンがなくても、恐くて外出はできないかな。
それはさておき、コロナ禍が収まった後の世界、社会の展望を最上敏樹さん(国際法学者、早稲田大学教授)は、書かれています:
「このあとの世界」
夜が明けたら
この、閉ざされた自粛の日々が終わったら、ぼくはコンサートに行こうか、バーゼルに帰って満天の星を仰ぎ見ようか。いや、その前にポール・エリュアール(1895~1952)と唱和して、こうつぶやこうか。
願望を失った放心の上に
むき出しの孤独の上に
死の行進の上に
ぼくはきみの名を書く
とり戻した健康の上に
過ぎ去った災厄の上に
想い出のない希望の上に
ぼくはきみの名を書く
そして言葉の力をふるい起し
ぼくは再び生き始める
ぼくはきみを見つけるために
きみを名付けるために生まれた
自由、と
全部で20連かrなり、「~の上に」のくり返しが心に響く詩だ。1942年ナチス・ドイツによるフランス占領への抵抗として書かれたこの詩を、コロナウイルスとの闘いの中で、何度も思い出す。<中略>
未来からの解放
また白紙からやり直すのだ、という言葉も耳にした。強い意志に立ち、希望をこめてのことだろう。
しかし、自然を克服し自然の脅威から永遠に自由であるような世界は、いや、そういう世界があるという幻想はもうよみがえらないし、よみがえる必要もない。無限に成長する経済という夢物語も、そろそろ捨てなければならない。感染者や死者が刻々と増える危機のまっただ中、この国の首相がまだ「経済のV字回復」などと言ってるのを聞き、いったい何を考えているのだろうと思った。
まっさらになった場所で一からやり直す、という目標がどれほどむごいものであるか、大津波で大切なあらゆるものを流された東日本被災地の人々には、よくよく実感でっきるだろう。「あとを更地にした、さあここで一からやり直せ」と言うのは、ときに責め苦でしかなくなる。
<中略>
T.S.エリオット(1888~1965)の
詩の中に、「過去からの解放を、そして未来からの解放を」という言葉がある。そう、未来からの解放を考えることが、いま、必要なのだ。
<中略>
希望と連帯
5月中旬、いくつかの英紙や米紙に、新しい時代への希望を感じさせる記事が載っていた。<中略>
被害が大きく、とりわけ弱者や少数奢が置き去りにされる米国で、先住民の集団に対して募金が寄せられた。寄せたのはアイルランドの人々。寄付された個々の額は10ドルとか20ドルとか、庶民が出せるささやかな浄財である。それを多くの市民が差し出した。
なぜ7000キロも遠くのアイルランドから、アメリカの先住民たちに寄付がされたのか。1847年、アイルランドで飢饉が起きて人々が苦しみ抜いた。それを知ったアメリカ先住民たちが、自分たちも十分以上に差別と貧しさに苦しんでいたのに、ひとごととは思えず募金し、できる限りのお金を送ったのだ。総額170ドルだったという。
貨幣価値のちがいこそあれ、当時としてもささやかな額でしかない。だがアイルランドの人たちには、この時の恩義をずっと忘れずにきた。語り継ぎ、いつか恩返しをしようとしてきた。危機はこうして、人間の尊厳も生み出す。
お礼のメッセージに、アメリカ先住民の一人は万感の思いを込めた。「私たちの苦難に対し、このような連帯を送ってくださり。ありがとう。私たちに寄り添ってくださり、ありがとう」。このあとの世界に残すべき遺産だ。
<中略>
遠く離れた国で誰もが同じ苦しみの下にあるということを初めて実感した。不幸の中の連帯ではあるが、それは利益に基づく結束よりもはるかに強い。
<引用以上>
言葉は、いのち。心に届く。うそで、うそでなくてもほんきでない、うわべだけのことばは、心に届かない、心に響かない。言葉は、行動によって歴史に刻まれる。いいことも、悪いことも。「私は戦後生まれなものですから、歴史を持ち出されたら困ります」と、沖縄の玉城知事の抗議を、こんな逃げの、拒絶の言葉でしか返せない首相って。。詩人は、芸術家は、小説家は、音楽家は、想像力がなければ伝える言葉を、表現を持てない。まして、政治家、経済人は、それ以上に、弱者に寄り添える想像力がなければ、なる資格はない。
それはさておき、コロナ禍が収まった後の世界、社会の展望を最上敏樹さん(国際法学者、早稲田大学教授)は、書かれています:
「このあとの世界」
夜が明けたら
この、閉ざされた自粛の日々が終わったら、ぼくはコンサートに行こうか、バーゼルに帰って満天の星を仰ぎ見ようか。いや、その前にポール・エリュアール(1895~1952)と唱和して、こうつぶやこうか。
願望を失った放心の上に
むき出しの孤独の上に
死の行進の上に
ぼくはきみの名を書く
とり戻した健康の上に
過ぎ去った災厄の上に
想い出のない希望の上に
ぼくはきみの名を書く
そして言葉の力をふるい起し
ぼくは再び生き始める
ぼくはきみを見つけるために
きみを名付けるために生まれた
自由、と
全部で20連かrなり、「~の上に」のくり返しが心に響く詩だ。1942年ナチス・ドイツによるフランス占領への抵抗として書かれたこの詩を、コロナウイルスとの闘いの中で、何度も思い出す。<中略>
未来からの解放
また白紙からやり直すのだ、という言葉も耳にした。強い意志に立ち、希望をこめてのことだろう。
しかし、自然を克服し自然の脅威から永遠に自由であるような世界は、いや、そういう世界があるという幻想はもうよみがえらないし、よみがえる必要もない。無限に成長する経済という夢物語も、そろそろ捨てなければならない。感染者や死者が刻々と増える危機のまっただ中、この国の首相がまだ「経済のV字回復」などと言ってるのを聞き、いったい何を考えているのだろうと思った。
まっさらになった場所で一からやり直す、という目標がどれほどむごいものであるか、大津波で大切なあらゆるものを流された東日本被災地の人々には、よくよく実感でっきるだろう。「あとを更地にした、さあここで一からやり直せ」と言うのは、ときに責め苦でしかなくなる。
<中略>
T.S.エリオット(1888~1965)の
詩の中に、「過去からの解放を、そして未来からの解放を」という言葉がある。そう、未来からの解放を考えることが、いま、必要なのだ。
<中略>
希望と連帯
5月中旬、いくつかの英紙や米紙に、新しい時代への希望を感じさせる記事が載っていた。<中略>
被害が大きく、とりわけ弱者や少数奢が置き去りにされる米国で、先住民の集団に対して募金が寄せられた。寄せたのはアイルランドの人々。寄付された個々の額は10ドルとか20ドルとか、庶民が出せるささやかな浄財である。それを多くの市民が差し出した。
なぜ7000キロも遠くのアイルランドから、アメリカの先住民たちに寄付がされたのか。1847年、アイルランドで飢饉が起きて人々が苦しみ抜いた。それを知ったアメリカ先住民たちが、自分たちも十分以上に差別と貧しさに苦しんでいたのに、ひとごととは思えず募金し、できる限りのお金を送ったのだ。総額170ドルだったという。
貨幣価値のちがいこそあれ、当時としてもささやかな額でしかない。だがアイルランドの人たちには、この時の恩義をずっと忘れずにきた。語り継ぎ、いつか恩返しをしようとしてきた。危機はこうして、人間の尊厳も生み出す。
お礼のメッセージに、アメリカ先住民の一人は万感の思いを込めた。「私たちの苦難に対し、このような連帯を送ってくださり。ありがとう。私たちに寄り添ってくださり、ありがとう」。このあとの世界に残すべき遺産だ。
<中略>
遠く離れた国で誰もが同じ苦しみの下にあるということを初めて実感した。不幸の中の連帯ではあるが、それは利益に基づく結束よりもはるかに強い。
<引用以上>
言葉は、いのち。心に届く。うそで、うそでなくてもほんきでない、うわべだけのことばは、心に届かない、心に響かない。言葉は、行動によって歴史に刻まれる。いいことも、悪いことも。「私は戦後生まれなものですから、歴史を持ち出されたら困ります」と、沖縄の玉城知事の抗議を、こんな逃げの、拒絶の言葉でしか返せない首相って。。詩人は、芸術家は、小説家は、音楽家は、想像力がなければ伝える言葉を、表現を持てない。まして、政治家、経済人は、それ以上に、弱者に寄り添える想像力がなければ、なる資格はない。
閲覧(3613)
| カテゴリー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
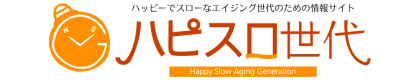




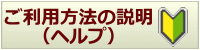
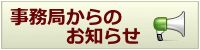

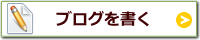
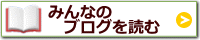
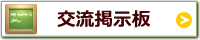
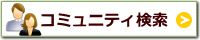
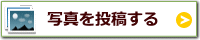
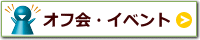
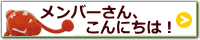
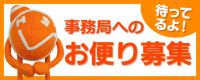
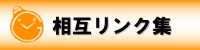


 前の日記
前の日記