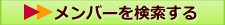tinc さんの日記
2020
11月
28
(土)
21:43
本文
最近新しくカスタマーサポートの仕事に就いた。現在のところ受ける連絡の多くは苦情であり、電話口で苦言を呈されたり罵倒されたり恫喝されたりしながら謝罪の意を伝えることが現在の私の主な業務の内容である。
まだ2日間しか勤務していないこともあって勤務先の内情等は不明ながら、サポート対象の商材に関する情報が少なかったり古かったり整理されていなかったり、外部からいくつも訴訟を起こされている様子であることが見ようと思えば見られてしまうところに書かれていたり、社の専務を名乗る人物が突然現場へやってきて私に昼食をご馳走してくれたりという勤務していて戸惑いや驚きの絶えない環境であるように感じている。私を正社員採用するくらいだから所謂ブラック企業というやつなのかもしれない。しかし私のほうも云わばブラック人材なのだからその点はお互い様である。
業務で苦情を受けて相手方と話しているといろいろと考えることがあって面白い。相手は言葉の上で何を述べていて、それは実際に求めているところとどれくらい一致していて、こちらはそれに対して何を伝えれば解決と呼ぶに値するところへ着地させられるか。相手と呼吸を合わせて相手が次にどんな動きに出るかを想像しながら自分の動きを調整する。ダンスの経験は無いながら、ペアダンスを踊るというのはこういう感じのするものだろうかという想像が頭をよぎる。
ところで日常「苦情」と似た使い方をされる言葉に「クレーム」がある。英語のclaimという言葉は「当然の権利として主張する」というところから来ていると聞くので、感情の訴えと権利の主張ということで意味するところは大分違うのが本当であると思う。行政の処分や法的な判断に対しては異議や不服の「申立」があるので、こちらのほうがclaimに近い概念のような気がする。
権利を主張するという行為では法律等何らかの規則や規定に基いて事実を争ったりまたはその規則や規定自体の評価や解釈について相手方との齟齬を述べたりする。感情の訴えにはそのような多くの人へ開かれた構造が存在せず、法で規定されている概念の中で近いものは「精神的苦痛」になるのだろうかと思う。このように考えると「苦情」という言葉が「クレーム」に置き換わるのも理解しやすくなるような気がする。自身の感情の問題を他人に解決させて満足を得ようとする行為が正当性を帯びる権利主張に含まれるようになれば、苦痛を感じている人やより多くの利益を得たい人はひとまず誰かへ訴え出るということをしやすくなるからだ。
この言葉の変遷をどのように評価するのが適切であるかということは私には分からないし、私自身にとって良いことか悪いことかということも単純に云えない。私は誰かが何かを言うことに対する制限は可能な限り少ないほうが良いと思うのでものを言いやすいということは良いことであると思う一方で、本来自身で解決すべきことでも他人がしてくれるのが当然であるという考えには賛同し難いので、感情的な訴えを全て権利主張に包含してしまうことは誤りであると思う。ただそれも何の事項のどの程度までが「自身で解決すべきこと」であるのかを明確に云うことは難しく、例えば仮に自助努力の義務というものを極大に拡張すれば法律も医療も何もかも不要となり社会は想像の困難なほどの混沌に陥るか、あるいはその反対に完全に管理され人間性をおよそ持ち合わせぬ管理体系になるかのどちらかだろうと思う。どちらも望ましくない。
世は全てバランスで成り立っている。
ある企業に雇用されカスタマーサポートの部署に在籍し一人のオペレーターとして誰かと会話するということは一個人として他者と対話するということとは大きく異なるため、苦言を呈されているのも罵倒されているのも恫喝されているのも私であって私でないようなところがある。しかしこれは私がかつて被雇用者として行っていた人材派遣会社の営業職であってもカフェスタッフであっても同じことで、相手と物理的に対面する機会が多いとそれが本当のその人であると思いがちであるが、ひとの本当の姿というのは本来分かりにくいものであるし存在するか否かも不明のものである。顔を合わせて話をすればいろいろと感じることはあるだろうが、それらは全て錯覚かもしれない。何かを知覚することとその何かが存在することは別である。
昨日別部署の先輩と喫煙所で一緒になった際、その先輩は「よくサポートなんてやろうと思ったね。上司からどやされるのはまだ我慢するとしても、客からまで訳わかんない文句ばっかり言われて過ごすなんて絶対無理」と吐き捨てるかのように言っていた。私はこのブログにも書かせて頂いたことのある、前職の退職の発端を思い出した。それはある上司が自宅に仕事を持ち帰って私事として行ってこいと私に命じたことであった。その時は当該の上司がその上司の庇護を受けていたこと等もあって私は辞めてしまったのであるが、今度同じようなことがあれば法的に争うことを試みてみてもよいのかもしれないと思う。少なくとも日本の現行の労働法においては被雇用者は強力に保護された立場にある。もし相手方の力量や政治動向その他世の何事かのバランスの要因で敗訴に終わるとしても、そういえばひとを公に告訴するということをしたことが無いので経験してみるのも面白いかもしれない。
裁判というものは時間と費用のかかるものであると聞くから、少しずつ貯金して弁護士費用を出せるようにしておこう。
まだ2日間しか勤務していないこともあって勤務先の内情等は不明ながら、サポート対象の商材に関する情報が少なかったり古かったり整理されていなかったり、外部からいくつも訴訟を起こされている様子であることが見ようと思えば見られてしまうところに書かれていたり、社の専務を名乗る人物が突然現場へやってきて私に昼食をご馳走してくれたりという勤務していて戸惑いや驚きの絶えない環境であるように感じている。私を正社員採用するくらいだから所謂ブラック企業というやつなのかもしれない。しかし私のほうも云わばブラック人材なのだからその点はお互い様である。
業務で苦情を受けて相手方と話しているといろいろと考えることがあって面白い。相手は言葉の上で何を述べていて、それは実際に求めているところとどれくらい一致していて、こちらはそれに対して何を伝えれば解決と呼ぶに値するところへ着地させられるか。相手と呼吸を合わせて相手が次にどんな動きに出るかを想像しながら自分の動きを調整する。ダンスの経験は無いながら、ペアダンスを踊るというのはこういう感じのするものだろうかという想像が頭をよぎる。
ところで日常「苦情」と似た使い方をされる言葉に「クレーム」がある。英語のclaimという言葉は「当然の権利として主張する」というところから来ていると聞くので、感情の訴えと権利の主張ということで意味するところは大分違うのが本当であると思う。行政の処分や法的な判断に対しては異議や不服の「申立」があるので、こちらのほうがclaimに近い概念のような気がする。
権利を主張するという行為では法律等何らかの規則や規定に基いて事実を争ったりまたはその規則や規定自体の評価や解釈について相手方との齟齬を述べたりする。感情の訴えにはそのような多くの人へ開かれた構造が存在せず、法で規定されている概念の中で近いものは「精神的苦痛」になるのだろうかと思う。このように考えると「苦情」という言葉が「クレーム」に置き換わるのも理解しやすくなるような気がする。自身の感情の問題を他人に解決させて満足を得ようとする行為が正当性を帯びる権利主張に含まれるようになれば、苦痛を感じている人やより多くの利益を得たい人はひとまず誰かへ訴え出るということをしやすくなるからだ。
この言葉の変遷をどのように評価するのが適切であるかということは私には分からないし、私自身にとって良いことか悪いことかということも単純に云えない。私は誰かが何かを言うことに対する制限は可能な限り少ないほうが良いと思うのでものを言いやすいということは良いことであると思う一方で、本来自身で解決すべきことでも他人がしてくれるのが当然であるという考えには賛同し難いので、感情的な訴えを全て権利主張に包含してしまうことは誤りであると思う。ただそれも何の事項のどの程度までが「自身で解決すべきこと」であるのかを明確に云うことは難しく、例えば仮に自助努力の義務というものを極大に拡張すれば法律も医療も何もかも不要となり社会は想像の困難なほどの混沌に陥るか、あるいはその反対に完全に管理され人間性をおよそ持ち合わせぬ管理体系になるかのどちらかだろうと思う。どちらも望ましくない。
世は全てバランスで成り立っている。
ある企業に雇用されカスタマーサポートの部署に在籍し一人のオペレーターとして誰かと会話するということは一個人として他者と対話するということとは大きく異なるため、苦言を呈されているのも罵倒されているのも恫喝されているのも私であって私でないようなところがある。しかしこれは私がかつて被雇用者として行っていた人材派遣会社の営業職であってもカフェスタッフであっても同じことで、相手と物理的に対面する機会が多いとそれが本当のその人であると思いがちであるが、ひとの本当の姿というのは本来分かりにくいものであるし存在するか否かも不明のものである。顔を合わせて話をすればいろいろと感じることはあるだろうが、それらは全て錯覚かもしれない。何かを知覚することとその何かが存在することは別である。
昨日別部署の先輩と喫煙所で一緒になった際、その先輩は「よくサポートなんてやろうと思ったね。上司からどやされるのはまだ我慢するとしても、客からまで訳わかんない文句ばっかり言われて過ごすなんて絶対無理」と吐き捨てるかのように言っていた。私はこのブログにも書かせて頂いたことのある、前職の退職の発端を思い出した。それはある上司が自宅に仕事を持ち帰って私事として行ってこいと私に命じたことであった。その時は当該の上司がその上司の庇護を受けていたこと等もあって私は辞めてしまったのであるが、今度同じようなことがあれば法的に争うことを試みてみてもよいのかもしれないと思う。少なくとも日本の現行の労働法においては被雇用者は強力に保護された立場にある。もし相手方の力量や政治動向その他世の何事かのバランスの要因で敗訴に終わるとしても、そういえばひとを公に告訴するということをしたことが無いので経験してみるのも面白いかもしれない。
裁判というものは時間と費用のかかるものであると聞くから、少しずつ貯金して弁護士費用を出せるようにしておこう。
閲覧(1986)
| カテゴリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
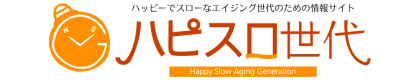
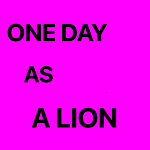




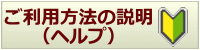
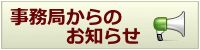

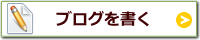
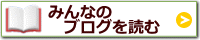
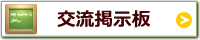
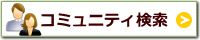
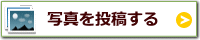
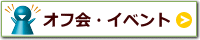
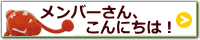
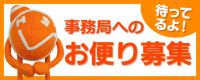
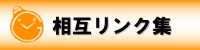


 前の日記
前の日記