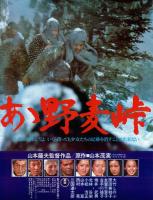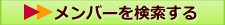松任谷 彩 さんの日記
2020
1月
31
(金)
16:24
本文
「よ~し、旅に出よう」の二回目となります。
飛騨高山の、そのまた奥に「古川」と云う寒村があります。
明治から大正時代、まだ汽車も通らぬ時代に、13歳前後の娘達が片道130kmの道のりを歩いて往復してました。毎年2月の半ばを過ぎる頃、野麦峠を通って岡谷・諏訪の製糸工場に「糸ひき」として働きに行きます。
帰りは、僅かな現金収入を抱えて冬の野麦峠を越え、両親の待つ「古川」に戻ります。
女工哀史には粗悪な食事、長時間労働、低賃金が定説になっていますが、工女たちに言わせると『それでも家の仕事より楽だった』と、答えています。
それだけ、彼女たちの置かれた環境は、貧乏に取り憑かれていました。
それも、そのはず、彼女たちは「口減らし」のために出されたのです。
しかし、そうは言っても、家を出る時は、親と子の別れがいつまでも続きます。
『ええか、しんぼうするんやぞ。ためらっていってこいよ』
(気おつけて行きなさい)
『ツォッツアマ(お父さん)も病気しなれんよ』
(病気にかからないように)
実際の野麦峠に立つと、昔の面影は全くありません。景観も良くありませんし「高山方向」は山で囲まれて見えません。
女工さん達の云う「郷里が見える」は『乗鞍岳』だった訳です。
やたらと観光用に造られた石碑や、コンクリート製の記念館が多い。
それでは、行って見る価値があったの?
とんでもない。長々と説明した「女工哀史」を背負ってこそ本当の旅と云えます。
一つ、加えます。
「野麦」とは、凶作の年に実を結び、里人が飢えをしのいだ云われるクマザサの実のこと。峠一帯を覆っていたことから呼び名になりました。
また「ノウミ」がなまったとの説もあります。諏訪地方の製糸工場で身ごもった工女が、峠でよく流産したことから「野産峠」とも言われてます。
※昭和54年に製作された映画『あゝ野麦峠』の予行編がありました。
「大竹しのぶ」さんの主演 ↓
https://www.youtube.com/watch?v=eEqpQVHwKjo
飛騨高山の、そのまた奥に「古川」と云う寒村があります。
明治から大正時代、まだ汽車も通らぬ時代に、13歳前後の娘達が片道130kmの道のりを歩いて往復してました。毎年2月の半ばを過ぎる頃、野麦峠を通って岡谷・諏訪の製糸工場に「糸ひき」として働きに行きます。
帰りは、僅かな現金収入を抱えて冬の野麦峠を越え、両親の待つ「古川」に戻ります。
女工哀史には粗悪な食事、長時間労働、低賃金が定説になっていますが、工女たちに言わせると『それでも家の仕事より楽だった』と、答えています。
それだけ、彼女たちの置かれた環境は、貧乏に取り憑かれていました。
それも、そのはず、彼女たちは「口減らし」のために出されたのです。
しかし、そうは言っても、家を出る時は、親と子の別れがいつまでも続きます。
『ええか、しんぼうするんやぞ。ためらっていってこいよ』
(気おつけて行きなさい)
『ツォッツアマ(お父さん)も病気しなれんよ』
(病気にかからないように)
実際の野麦峠に立つと、昔の面影は全くありません。景観も良くありませんし「高山方向」は山で囲まれて見えません。
女工さん達の云う「郷里が見える」は『乗鞍岳』だった訳です。
やたらと観光用に造られた石碑や、コンクリート製の記念館が多い。
それでは、行って見る価値があったの?
とんでもない。長々と説明した「女工哀史」を背負ってこそ本当の旅と云えます。
一つ、加えます。
「野麦」とは、凶作の年に実を結び、里人が飢えをしのいだ云われるクマザサの実のこと。峠一帯を覆っていたことから呼び名になりました。
また「ノウミ」がなまったとの説もあります。諏訪地方の製糸工場で身ごもった工女が、峠でよく流産したことから「野産峠」とも言われてます。
※昭和54年に製作された映画『あゝ野麦峠』の予行編がありました。
「大竹しのぶ」さんの主演 ↓
https://www.youtube.com/watch?v=eEqpQVHwKjo
閲覧(3290)
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
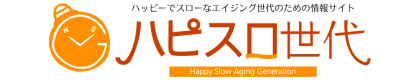





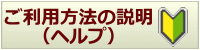
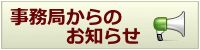

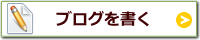
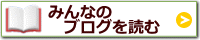
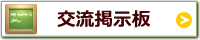
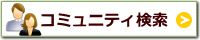
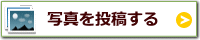
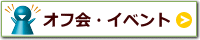
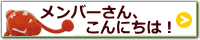
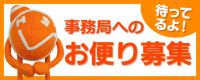
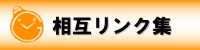


 前の日記
前の日記