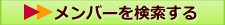風まかせ さんの日記
2020
1月
12
(日)
10:38
本文
文学のなかのおいしいもの
三四郎が食べたライスカレー
夏目漱石『三四郎』
「昼飯を食ひに下宿へ帰らふと思ったら、昨日ポンチ画をかいた男が来て、おいおいと云ひながら、本郷の軒淀見軒(よどみけん)と云ふ所に引張って行って、ライスカレーを食はした」
『三四郎』は、明治四十一年に朝日の新聞小説として書かれた。これはその一節。
熊本の高等学校を卒業し、帝国大学に入るべく花の東京へ出てきた三四郎。熊本では天下のエリートであったのに、東の都では関心を払う者とていない。のんびりした田舎の生活しか知らなかった三四郎は、東京の街に、人に、文化に大きなショックを受ける。
「三四郎が東京で驚ひたものは沢山ある。第一でんしゃのちんちん鳴るので驚ひた。それからそのちんちん鳴る間に、非常に多くの人間が乗ったり降りたりするので驚ひた。…尤も驚ひたのは、どこまで行っても東京が無くならないと云ふ事で合った。
…そして凡ての物が破壊されつつある様に見える。そして凡ての物が又同時に建設しつつある様に見える。大変な動き方である」。見るもの、聞くもののすべてに素直に感動する三四郎は、大学の授業が始まってまもなく、同じ授業をとる友人にライスカレーを食べに行こうと誘われる。
明治の末、まだ洋食はめずらしく、家庭ではもちろん、地方ではめったに食べることができない「ハイカラ」な食べ物であった。
ポンチ画(漫画<筆者注>)を描いていた友人、与次郎は、ある日授業に出なかった三四郎にこういってから誘う。
「おい何故休んだ。今日は伊太利人がマカロニーを如何にして食ふかと云ふ講義を聞いた」。
与次郎が誇らしげに淀見軒(よどみけん)のライスカレーに三四郎を誘ったのも、東京にはこんなハイカラな洋食があるんだぞ、という自慢だったのだろう。
大学近くのハイカラな店。帝大生や大学教授や学者が集まってきて、学問と文化のアカデミックな香りが漂う。
ある者は、口角泡で文学論を闘わせ、ある者は静かにドイツ語の原書に栞をはさんで、異国の香りライスカレーを食したことだろう。
いまは淀見軒も過去の記憶となってしまったが、同じ本郷、東大の正門前にある「万定(まんさだ)」という店が当時の面影をしのばせる。
二つの店とも、もともとは食べ物屋ではなく、果物を置いたフルーツパーラーであった。
ハイカラでモダンなフルーツパーラーが、食べ盛りの学生に出したメニューがライスカレーであった。
日本の文献に「カレー」という言葉が初めて登場したのは福沢諭吉の、「日→中→英」の簡略辞書『華英通語』(一八六〇<安政七>年)であったという。
その後の明治五年に『西洋料理指南』『西洋料理通』という二冊の本が、日本人向けにカレーの作り方を伝える。
カレーはインド料理ではなく西洋料理として日本に伝わった。当時は一部のホテルでしか味わえない高級メニューだったが、明治の中ごろ、『婦女雑誌』が即席カレーの作り方を載せ、その後、婦人雑誌が続々と、カレー料理法を紹介し、広く家庭の食卓におなじみのメニューとなる。
(具にもよるが)安くてうまくて、簡単なカレーは日本人に愛され、第二次世界大戦の日本軍には『軍隊調理法』にカレーのレシピが残っているほどである。
胸いっぱいの希望と、学問への情熱を抱いて東京にやって来た三四郎は、ライスカレーの味については何も語っていないが、異国の香りのなかに、モダニズムや文化の香りを感じていたのだろう。
現代はともかく、昔の若者にとってライスカレーは、希望あふれる「青春のメインディッシュ」であった。
ところでライスカレーとカレーライスはどうちがう。結論からいうと、もちろん同じものである。
かつて仕事仲間と「議論」したことがある。大食漢は、カレーはオカズだろう、ライスが主役だからライスカレーだという。
食べ盛りの子どもをかかえる主婦は、カレーは汁かけ飯の一種だからライスカレーで、小麦粉でいくらでものばせる経済料理だと付け加える。
漱石は『三四郎』のなかでライスカレーと記している。若者の好物ととらえているのだろう。
ぼくの亡母は、戦前、東京・新宿の武蔵野館で映画をみて、同じ新宿の中村屋で「カリーライス」を食べるのがデートコースだったという。
カレーライスはハイカラなイメージがあった、そしてハイカラな人を「ハイカった人」というという。「徘徊」もこう考えてみましょうか。
参考/「三四郎」(新潮文庫)
三四郎が食べたライスカレー
夏目漱石『三四郎』
「昼飯を食ひに下宿へ帰らふと思ったら、昨日ポンチ画をかいた男が来て、おいおいと云ひながら、本郷の軒淀見軒(よどみけん)と云ふ所に引張って行って、ライスカレーを食はした」
『三四郎』は、明治四十一年に朝日の新聞小説として書かれた。これはその一節。
熊本の高等学校を卒業し、帝国大学に入るべく花の東京へ出てきた三四郎。熊本では天下のエリートであったのに、東の都では関心を払う者とていない。のんびりした田舎の生活しか知らなかった三四郎は、東京の街に、人に、文化に大きなショックを受ける。
「三四郎が東京で驚ひたものは沢山ある。第一でんしゃのちんちん鳴るので驚ひた。それからそのちんちん鳴る間に、非常に多くの人間が乗ったり降りたりするので驚ひた。…尤も驚ひたのは、どこまで行っても東京が無くならないと云ふ事で合った。
…そして凡ての物が破壊されつつある様に見える。そして凡ての物が又同時に建設しつつある様に見える。大変な動き方である」。見るもの、聞くもののすべてに素直に感動する三四郎は、大学の授業が始まってまもなく、同じ授業をとる友人にライスカレーを食べに行こうと誘われる。
明治の末、まだ洋食はめずらしく、家庭ではもちろん、地方ではめったに食べることができない「ハイカラ」な食べ物であった。
ポンチ画(漫画<筆者注>)を描いていた友人、与次郎は、ある日授業に出なかった三四郎にこういってから誘う。
「おい何故休んだ。今日は伊太利人がマカロニーを如何にして食ふかと云ふ講義を聞いた」。
与次郎が誇らしげに淀見軒(よどみけん)のライスカレーに三四郎を誘ったのも、東京にはこんなハイカラな洋食があるんだぞ、という自慢だったのだろう。
大学近くのハイカラな店。帝大生や大学教授や学者が集まってきて、学問と文化のアカデミックな香りが漂う。
ある者は、口角泡で文学論を闘わせ、ある者は静かにドイツ語の原書に栞をはさんで、異国の香りライスカレーを食したことだろう。
いまは淀見軒も過去の記憶となってしまったが、同じ本郷、東大の正門前にある「万定(まんさだ)」という店が当時の面影をしのばせる。
二つの店とも、もともとは食べ物屋ではなく、果物を置いたフルーツパーラーであった。
ハイカラでモダンなフルーツパーラーが、食べ盛りの学生に出したメニューがライスカレーであった。
日本の文献に「カレー」という言葉が初めて登場したのは福沢諭吉の、「日→中→英」の簡略辞書『華英通語』(一八六〇<安政七>年)であったという。
その後の明治五年に『西洋料理指南』『西洋料理通』という二冊の本が、日本人向けにカレーの作り方を伝える。
カレーはインド料理ではなく西洋料理として日本に伝わった。当時は一部のホテルでしか味わえない高級メニューだったが、明治の中ごろ、『婦女雑誌』が即席カレーの作り方を載せ、その後、婦人雑誌が続々と、カレー料理法を紹介し、広く家庭の食卓におなじみのメニューとなる。
(具にもよるが)安くてうまくて、簡単なカレーは日本人に愛され、第二次世界大戦の日本軍には『軍隊調理法』にカレーのレシピが残っているほどである。
胸いっぱいの希望と、学問への情熱を抱いて東京にやって来た三四郎は、ライスカレーの味については何も語っていないが、異国の香りのなかに、モダニズムや文化の香りを感じていたのだろう。
現代はともかく、昔の若者にとってライスカレーは、希望あふれる「青春のメインディッシュ」であった。
ところでライスカレーとカレーライスはどうちがう。結論からいうと、もちろん同じものである。
かつて仕事仲間と「議論」したことがある。大食漢は、カレーはオカズだろう、ライスが主役だからライスカレーだという。
食べ盛りの子どもをかかえる主婦は、カレーは汁かけ飯の一種だからライスカレーで、小麦粉でいくらでものばせる経済料理だと付け加える。
漱石は『三四郎』のなかでライスカレーと記している。若者の好物ととらえているのだろう。
ぼくの亡母は、戦前、東京・新宿の武蔵野館で映画をみて、同じ新宿の中村屋で「カリーライス」を食べるのがデートコースだったという。
カレーライスはハイカラなイメージがあった、そしてハイカラな人を「ハイカった人」というという。「徘徊」もこう考えてみましょうか。
参考/「三四郎」(新潮文庫)
閲覧(1673)
| カテゴリー | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |







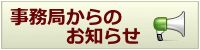

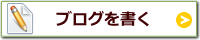
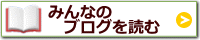
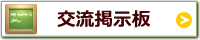
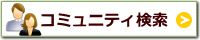
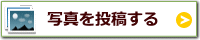
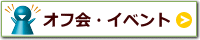
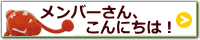




 前の日記
前の日記