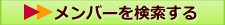tinc さんの日記
2020
1月
10
(金)
13:44
本文
数か月前に新しい仕事に就いてからほどなくして、私は統合失調症という精神病を発症した。かつて精神分裂病と呼ばれていたこの病気は、比較的ありふれているのに発現の仕方が様々で、幻聴、幻視、妄想といった異常なものの出現であったり、表情や思考、発語の減少といった正常な活力の減退であったりすると聞く。
私に目をつけたのは幻聴だった。ある日の朝、自宅の洗面所で、周囲に誰もいない状況で「死ね」という声が私の耳にはっきりと聞こえた。それは男性の声のようでもあり女性の声のようでもあり、また子供の声にも老人の声にも聞こえた。これほど主体の印象が曖昧であるにもかかわらず、誰かが私に「死ね」と声をかけているということは疑念なく私に認識されてしまった。私は職場へ欠勤の連絡もせず、最低限の身支度だけを終えるや否や通りへ出てタクシーに乗り、駅前の精神科クリニックを受診した。
ドクターは私の耳が絶え間ない幻聴に支配されており外部の(真に存在する方の)声が聞こえないことを察し、紙に文字を書いて私に「入院設備のある病院へ行き、これから自分が作成する紹介状を渡すように」と伝えた。私はそうした。そしてその日からつい昨日まで入院していた。
入院直後から投薬が奏効し、2週間ほどで幻聴は概ね消失、残存するものも現実の声と区別がつくようになった。しかし入院という経験を経た後の私の頭を悩ませるのはもはや幻聴ではなく、事物を認識するとはいったいどういうことなのか、人間の脳の中の精神と呼ばれる部分に共通するものは何なのか、自分が体験している病気が精神というそもそもあやしげな領域で起こっているものであるのなら、それはどの程度客観化できるのか、といった問題の数々であった。これらの問題にとらわれ始めた私はナースはじめ病院関係者たちから警戒され、見舞いに来てくれた知人たちから「いつも通りだ」と異口同音に言われることで少しずつその警戒は解けていったようだった。
病状は早期に改善したが、病院の社会復帰プログラムのようなものに参加し、貯金を崩したり保険を解約したりして入院費を工面し、病院内外のソーシャルワーカー達と退院後の生活について計画しているうちに数か月が過ぎ、年が明け、職場からは解雇通知が届き、もうすぐ33歳になる私は殆どゼロ(病気を考慮すればマイナス)の状態から再び市井での生活を送ることになっている。
こうなって初めて実感するのだが、起こりうることはいつか起こるし、老病死苦から人間は逃れ得ないのだろう。普通に生きているというのは当たり前のことではない。他者の有形無形の支えと社会システム、人間に食される動植物たちの知られ得ぬ犠牲など、多くの前提があってたまたま成り立っていることだ。それを知ってはいても意識せず、大丈夫大丈夫と、何が大丈夫か知らぬままに高を括っていたのが今までの私であったように思う。このことを振り返りながらでなければ、生きていてもつまらないだろう。世間で評判の悪い日本国憲法にも、平和は国民の不断の努力によって維持されねばならぬというようなことが書いてあったっけ。悪評が立っていても良いことが書いてあるものだ。
それはさておき、まずは働き口の確保と、事情を一部でも知る知人たちへの礼状書きから初めている。返事の早い知人たちはそれぞれに、私の新たに抱えることになった病の原因を、幼少期の心の傷であるとか、仕事のしすぎだとか、内向的な性格に根ざすものだとか分析してくれているようだ。私はそれらを受けて自分の内面や過去を振り返りつつ、Nothing is what it seemsという英語の言い回しにもあるように、自分の中だけの結論を何かの正解のように思わないよう気をつけようとも思っている。
これを読んでくれている方がいるなら、誰か知らないがその人の健康を切に願う。もし病気になってしまったらその回復を、やはり切に願う。私にはあなたが回復するまでいつも通りの国民健康保険料を払うくらいしかできることはないけれど、あなたが払ってくれた保険料のおかげで私は破産せずに退院できたのである。
私に目をつけたのは幻聴だった。ある日の朝、自宅の洗面所で、周囲に誰もいない状況で「死ね」という声が私の耳にはっきりと聞こえた。それは男性の声のようでもあり女性の声のようでもあり、また子供の声にも老人の声にも聞こえた。これほど主体の印象が曖昧であるにもかかわらず、誰かが私に「死ね」と声をかけているということは疑念なく私に認識されてしまった。私は職場へ欠勤の連絡もせず、最低限の身支度だけを終えるや否や通りへ出てタクシーに乗り、駅前の精神科クリニックを受診した。
ドクターは私の耳が絶え間ない幻聴に支配されており外部の(真に存在する方の)声が聞こえないことを察し、紙に文字を書いて私に「入院設備のある病院へ行き、これから自分が作成する紹介状を渡すように」と伝えた。私はそうした。そしてその日からつい昨日まで入院していた。
入院直後から投薬が奏効し、2週間ほどで幻聴は概ね消失、残存するものも現実の声と区別がつくようになった。しかし入院という経験を経た後の私の頭を悩ませるのはもはや幻聴ではなく、事物を認識するとはいったいどういうことなのか、人間の脳の中の精神と呼ばれる部分に共通するものは何なのか、自分が体験している病気が精神というそもそもあやしげな領域で起こっているものであるのなら、それはどの程度客観化できるのか、といった問題の数々であった。これらの問題にとらわれ始めた私はナースはじめ病院関係者たちから警戒され、見舞いに来てくれた知人たちから「いつも通りだ」と異口同音に言われることで少しずつその警戒は解けていったようだった。
病状は早期に改善したが、病院の社会復帰プログラムのようなものに参加し、貯金を崩したり保険を解約したりして入院費を工面し、病院内外のソーシャルワーカー達と退院後の生活について計画しているうちに数か月が過ぎ、年が明け、職場からは解雇通知が届き、もうすぐ33歳になる私は殆どゼロ(病気を考慮すればマイナス)の状態から再び市井での生活を送ることになっている。
こうなって初めて実感するのだが、起こりうることはいつか起こるし、老病死苦から人間は逃れ得ないのだろう。普通に生きているというのは当たり前のことではない。他者の有形無形の支えと社会システム、人間に食される動植物たちの知られ得ぬ犠牲など、多くの前提があってたまたま成り立っていることだ。それを知ってはいても意識せず、大丈夫大丈夫と、何が大丈夫か知らぬままに高を括っていたのが今までの私であったように思う。このことを振り返りながらでなければ、生きていてもつまらないだろう。世間で評判の悪い日本国憲法にも、平和は国民の不断の努力によって維持されねばならぬというようなことが書いてあったっけ。悪評が立っていても良いことが書いてあるものだ。
それはさておき、まずは働き口の確保と、事情を一部でも知る知人たちへの礼状書きから初めている。返事の早い知人たちはそれぞれに、私の新たに抱えることになった病の原因を、幼少期の心の傷であるとか、仕事のしすぎだとか、内向的な性格に根ざすものだとか分析してくれているようだ。私はそれらを受けて自分の内面や過去を振り返りつつ、Nothing is what it seemsという英語の言い回しにもあるように、自分の中だけの結論を何かの正解のように思わないよう気をつけようとも思っている。
これを読んでくれている方がいるなら、誰か知らないがその人の健康を切に願う。もし病気になってしまったらその回復を、やはり切に願う。私にはあなたが回復するまでいつも通りの国民健康保険料を払うくらいしかできることはないけれど、あなたが払ってくれた保険料のおかげで私は破産せずに退院できたのである。
閲覧(3258)
| カテゴリー | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |







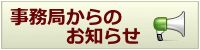

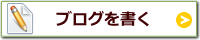
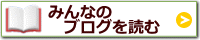
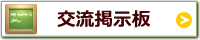
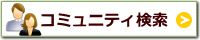
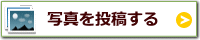
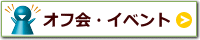
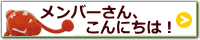




 前の日記
前の日記