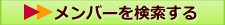風まかせ さんの日記
2020
1月
10
(金)
10:00
本文
文学のなかのおいしいもの
はじめての「朝ごはん」
井上靖『しろばんば』
(新聞にかつて、井上靖がノーベル賞候補にあがったと載っていた)
旅先の朝食はどうしてあんなに輝いていたのだろう。いつもは一膳しか食べないのに、いくらなんでも箸がすすむ。洪作もそうであった。「ばあちゃ」から「いくら何でも、もうやめとき」と注意されても、「だって、まだ卵焼きが残っている」といいながら四杯目の茶碗を突き出した。
洪作は伊豆半島の天城山麓の山村で育った。林野管理局が村で一番立派な建物、雑貨屋はたった一軒、あとは農家が並ぶひっそりとした山村だった。父は軍医で任地を転々としていた。小学生の洪作には、はっきりとした理由はわからなかったが、父母と別の地で「ばあちゃ」と呼ぶ義理の祖母とともに暮らしていた。
「その頃、と言いっても大正四、五年のこと」、洪作の住む天城の山村では、「夕闇のたちこめ始めた空間を綿屑のように浮遊している」小さい白い生物を、子供たちが口々に「しろばんば」と叫びながら追いかけて遊んでいた。
「しろばんばは〝白い老婆〟ということなのだろう」。夕闇が深くなると家の者が「早く来んとめし喰わせんぞ」などと子供たちを迎えに来たが、洪作はいつも一番遅くまで遊んでいた。
洪作の家の夕食は遅かったし、年をとったばあちゃが迎えに来ることもめったになかったので、友だちが誰もいなくなり夕闇があたりをすっかり閉じ込めてしまってからひとりで家へ歩いて帰った。
それは寂しいことのようだが、洪作には楽しかった。『しろばんば』は、親元から離れて暮らす小学生の洪作が、友だちや大人たちとの関わりの中で、様々な出来事を経験し、時には共感を、時には反感を抱きながら、徐々に大人への階段を上っていく物語。
洪作にとっての「事件」が起きた。馬車に乗って、軽便鉄道に乗って、それから大きい汽車に乗って、ばあちゃとふたりで父の住む豊橋へと行くというのである。
豊橋ははるか遠くの大都会、洪作にとっては未知の世界への旅でもある。出発の前の日、洪作はばあちゃにつかまえられて、足の指の一本一本にまで石鹸で洗われ、踵は皮が向けるほど軽石でしごかれた。
いつもより早く寝かされたが、嬉しくてなかなか寝つかれなかった。翌朝は、よそ行きの着物を着せられて馬車の駐車場へ行った。出発の合図の喇叭が鳴ると、近所の大人たちはいっせいに手を振り、子供たちは歓声とともに馬車を追いかけて駆け出した。
洪作は村中の興奮を背に、小さくなっていく村をあとにした。下田街道のゆるい傾斜を馬車で四時間も走り、終点の駅から美島町までは軽便鉄道に乗った。洪作は見知らぬ町を見た興奮で熱を出し、目を覚ますと沼津の駅前の旅館にいた。
翌朝は八時に目を覚ました。ばあちゃは汽車の時間まで寝ているようにというが、洪作はじっとなんかしていられない。窓の外を覗いて広場にたくさんの人がいるのを見学していると、朝食が食卓に並んでいた。
洪作はごくりと生唾を呑み込んだ。卵焼き、魚の干物、海苔、そんなものが一度に目に入ってきて、立派な椀の中で湯気を立てている味噌汁も運ばれる。ばあちゃが毎朝つくってくれる朝食は、ご飯と味噌汁と金山寺味噌だけ。毎日の変化といえば味噌汁の具と漬物の種が季節によって変わるだけだった。
ところがどうであろう。目の前の朝食はとんでもないご馳走である。洪作はどれから先に手をつけるべきか迷いながら、ゆっくりと時間をかけて食べた。四回目の茶碗を突き出したとき、ばあちゃに「もうやめとき」といわれて、ご飯はあきらめ卵焼きだけを食べたが、食事を終えると満腹でひっくり返った。洪作ははじめての旅館の、輝かしい朝食を心いっぱい味わった。そして旅館の天井を眺めながら、まだまだ先の大都会、豊橋のことと、未知の輝く「朝食」のことを考えていた。
旅館ではないが、向田邦子さんは、ほのぼの朝ごはんを綴っている。「(朝ごはんは)おみおつけでまず一膳のごはんを食べ、生卵か海苔、納豆は二膳目でないと箸をつけてはいけないというのである。ごはん一膳では、いつまでたっても今の大きさだよ、子供は二膳目のごはんで大きくなるものだ、と(父はおかしな理屈を)いうのである」。
ぼくの子どものころ。朝ごはんの生卵は、父だけが黄身だけをご飯にかけてよいことになっていた。そのときの父の朝ご飯は輝いて見えたが、大きくなって真似してみると、おいしくなかった。
*金山寺味噌/煎った大豆と大麦の麹をまぜて塩を加え、刻んだなすや瓜・ショウガなどを入れて熟成させたなめ味噌。和歌山県湯浅の名物。
参考/井上靖『しろばんば』新潮社文庫
向田邦子『夜中の薔薇』講談社文庫
はじめての「朝ごはん」
井上靖『しろばんば』
(新聞にかつて、井上靖がノーベル賞候補にあがったと載っていた)
旅先の朝食はどうしてあんなに輝いていたのだろう。いつもは一膳しか食べないのに、いくらなんでも箸がすすむ。洪作もそうであった。「ばあちゃ」から「いくら何でも、もうやめとき」と注意されても、「だって、まだ卵焼きが残っている」といいながら四杯目の茶碗を突き出した。
洪作は伊豆半島の天城山麓の山村で育った。林野管理局が村で一番立派な建物、雑貨屋はたった一軒、あとは農家が並ぶひっそりとした山村だった。父は軍医で任地を転々としていた。小学生の洪作には、はっきりとした理由はわからなかったが、父母と別の地で「ばあちゃ」と呼ぶ義理の祖母とともに暮らしていた。
「その頃、と言いっても大正四、五年のこと」、洪作の住む天城の山村では、「夕闇のたちこめ始めた空間を綿屑のように浮遊している」小さい白い生物を、子供たちが口々に「しろばんば」と叫びながら追いかけて遊んでいた。
「しろばんばは〝白い老婆〟ということなのだろう」。夕闇が深くなると家の者が「早く来んとめし喰わせんぞ」などと子供たちを迎えに来たが、洪作はいつも一番遅くまで遊んでいた。
洪作の家の夕食は遅かったし、年をとったばあちゃが迎えに来ることもめったになかったので、友だちが誰もいなくなり夕闇があたりをすっかり閉じ込めてしまってからひとりで家へ歩いて帰った。
それは寂しいことのようだが、洪作には楽しかった。『しろばんば』は、親元から離れて暮らす小学生の洪作が、友だちや大人たちとの関わりの中で、様々な出来事を経験し、時には共感を、時には反感を抱きながら、徐々に大人への階段を上っていく物語。
洪作にとっての「事件」が起きた。馬車に乗って、軽便鉄道に乗って、それから大きい汽車に乗って、ばあちゃとふたりで父の住む豊橋へと行くというのである。
豊橋ははるか遠くの大都会、洪作にとっては未知の世界への旅でもある。出発の前の日、洪作はばあちゃにつかまえられて、足の指の一本一本にまで石鹸で洗われ、踵は皮が向けるほど軽石でしごかれた。
いつもより早く寝かされたが、嬉しくてなかなか寝つかれなかった。翌朝は、よそ行きの着物を着せられて馬車の駐車場へ行った。出発の合図の喇叭が鳴ると、近所の大人たちはいっせいに手を振り、子供たちは歓声とともに馬車を追いかけて駆け出した。
洪作は村中の興奮を背に、小さくなっていく村をあとにした。下田街道のゆるい傾斜を馬車で四時間も走り、終点の駅から美島町までは軽便鉄道に乗った。洪作は見知らぬ町を見た興奮で熱を出し、目を覚ますと沼津の駅前の旅館にいた。
翌朝は八時に目を覚ました。ばあちゃは汽車の時間まで寝ているようにというが、洪作はじっとなんかしていられない。窓の外を覗いて広場にたくさんの人がいるのを見学していると、朝食が食卓に並んでいた。
洪作はごくりと生唾を呑み込んだ。卵焼き、魚の干物、海苔、そんなものが一度に目に入ってきて、立派な椀の中で湯気を立てている味噌汁も運ばれる。ばあちゃが毎朝つくってくれる朝食は、ご飯と味噌汁と金山寺味噌だけ。毎日の変化といえば味噌汁の具と漬物の種が季節によって変わるだけだった。
ところがどうであろう。目の前の朝食はとんでもないご馳走である。洪作はどれから先に手をつけるべきか迷いながら、ゆっくりと時間をかけて食べた。四回目の茶碗を突き出したとき、ばあちゃに「もうやめとき」といわれて、ご飯はあきらめ卵焼きだけを食べたが、食事を終えると満腹でひっくり返った。洪作ははじめての旅館の、輝かしい朝食を心いっぱい味わった。そして旅館の天井を眺めながら、まだまだ先の大都会、豊橋のことと、未知の輝く「朝食」のことを考えていた。
旅館ではないが、向田邦子さんは、ほのぼの朝ごはんを綴っている。「(朝ごはんは)おみおつけでまず一膳のごはんを食べ、生卵か海苔、納豆は二膳目でないと箸をつけてはいけないというのである。ごはん一膳では、いつまでたっても今の大きさだよ、子供は二膳目のごはんで大きくなるものだ、と(父はおかしな理屈を)いうのである」。
ぼくの子どものころ。朝ごはんの生卵は、父だけが黄身だけをご飯にかけてよいことになっていた。そのときの父の朝ご飯は輝いて見えたが、大きくなって真似してみると、おいしくなかった。
*金山寺味噌/煎った大豆と大麦の麹をまぜて塩を加え、刻んだなすや瓜・ショウガなどを入れて熟成させたなめ味噌。和歌山県湯浅の名物。
参考/井上靖『しろばんば』新潮社文庫
向田邦子『夜中の薔薇』講談社文庫
閲覧(1411)
| カテゴリー | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |







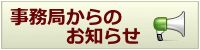

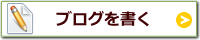
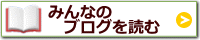
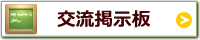
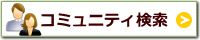
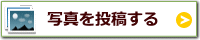
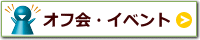
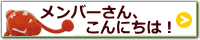




 前の日記
前の日記



 が、大変美味しくいただけます。
が、大変美味しくいただけます。