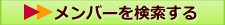Bishop さんの日記
2019
8月
15
(木)
21:59
本文
この光秀のブログを始めたのが2月2日。
以後6か月で11回、今回で12回目になりましたが、ここまで来て” しまった “と思いました。
というのも、表記のことをいろいろ調べてみると、なんとその説がこんなにあるとは・・・。
怨恨説から野望説、恐怖心説などなどウィキペディアにおいては57もの説があるんですね。
これをひとつひとつ勉強し、ブログで説明するのはかなり難しいと感じました。
その必要もないしね。
そこで、その57の説についてはウィキペディアを見ていただければそれで良いかなと考えます。
<ウィキペディア(Wikipedia)の「本能寺の変」で入力して下さい。>
ただ、それでだけでは、あまりにも手抜きブログであり、来年の大河ドラマの参考にならず、また私の思うところも書けないまま、なんとも間の抜けた終わり方になりますので、
二三の興味ある記事を勉強しましたのでその内容についてご紹介し、最後に私の思う所を書かせていただきます。
四国征伐回避説
信長の四国征伐を回避するために謀反を起こしたとする説です。
平成26年に発見された長宗我部元親から斎藤利三に宛てた書状がこの説を裏付けているそうです。
この書状は、信長に対して、元親が土佐国・阿波2郡のみの領有と上洛に応じるという内容です。
しかし、信長は長宗我部元親の四国領有を認めていたのに、その約束を翻し、四国攻めの準備をしていました。
もし、この四国攻めが実行されると、秀吉と三好笑岩(康長)(阿波の国主)の勝利になる。(当時、光秀-元親ラインに対して秀吉-康長ラインという図式があった。)
また、元親に対して光秀は面目が立たなくなる。
ということは、光秀も失脚させられる可能性が高くなる。
ということで、謀反に踏み切ったというものです。
共謀説(土岐明智家滅亡阻止説)
明智光秀の子の於隺丸(おづるまる)の子孫であると称しておられる明智憲三郎氏の説です。
※ 明智光秀 生存説(天海=光秀説/天海=秀満説)を唱えた明智滝朗氏は憲三郎氏のおじいさんです。
光秀は、信長の次なる野望、唐への侵攻を知っていました。
これが実行されると、自分はともかく明智一族はこの侵攻に駆り出され、それは一族の滅亡に繋がると危惧していました。
そんなとき、信長は家康を安土に呼び武田討伐の労をねぎらいました。
このとき、信長は光秀に家康を討たせて、徳川領を我が物にしようとしました。
光秀は、この計画を逆手に取り家康と結託し謀反を起こした。というものです。
上記の2説についても、いろんな意見があり、確たるものでは無いようです。
次に、これには私も「なるほど!」とうなりました(笑)
某ウェブサイトのブログにあった説です。
秀吉は中国の毛利氏と対峙していた時、四国の長宗我部氏も信長から討伐せよと命じられていました。
そこで、援軍を信長に乞うたところ、織田信孝を大将に丹羽長秀以下14,000の軍勢を応援に向かわせようとしていました。
信長は、光秀にも四国討伐の手助けをするように命令しましたが、長宗我部と親しくしている光秀にとってそれは出来ない相談でした。
長宗我部元親とは、信長を討つ約束までしている。もし元親を裏切って四国討伐に加担しようとすれば、元親は信長に光秀謀反の心有りとばらされてしまう。
したがって、どうしても四国討伐を阻止する必要があったわけです。
そこで、光秀はイエズス会のルイス・フロイスを動かそうとしたのです。
キリスト教布教のために信長と結託していたイエズス会ですが、なかなか信長は全面的な布教活動に協力してくれなかった。
徐々に、その関係は崩れていき、信長以外のスポンサーを見つけようとフロイスは思っていました。
光秀は、フロイスに「信長を討って、大伴宗麟を天下人にすることができるが・・・」
大伴宗麟は周囲の反対を押し切ってキリスト教に改宗した人で、ルイスは彼ならイエズス会の布教活動も進められると判断しました。
しかし、光秀にはその場での返事を保留し、大伴氏に相談したのです。
大伴宗麟は、光秀がそんな大それたことを考えていることに懸念を持ち、協力関係にあった秀吉にその事実を相談したのです。
秀吉はルイスに、「光秀の話には乗らず、お館様に光秀のたくらみを伝えよ!」とは言わなかったのです。
秀吉という人物も、立身出世を狙っていた狡猾な人間です。
彼はルイスに「大友宗麟は明智殿に協力する。だから明智殿も必ず信長公を誅してほしい」と光秀に言いなさいと・・・。
これが、光秀謀反の経緯であるという説です。
で、私の考えですが、
柴田勝家や佐久間など従来の家臣は織田家があって、自分がある。
織田家が繁栄することが、自らの出世に繋がるという忠誠心があります。
しかし、秀吉も家康も光秀も織田家譜代の家臣ではありません。
秀吉は貧乏な百姓上がりであるがゆえに、出世欲は人一倍強かったと思います。
家康は三河の松平家の嫡男として生まれ、いずれはお家再興し徳川の世を築きたいという気持ちはあったと思います。
光秀も、美濃は土岐氏という名家の出身である以上、いずれは天下にその名を轟かせたいと思っていたと思います。
また、光秀は斎藤道三に仕えており、道三が一油売りの商人から美濃国を下剋上により奪い取った生きざまを見てきています。
したがって、光秀は突発的にとか、怨恨でとか、誰かと共謀してとか、黒幕がいたとか、そういう次元の話では無いと思います。
理想とする国造り・・・それは応仁の乱以降、乱れに乱れた日本国の再建。戦に明け暮れる社会を終わらせる。そうした国造りの中心に土岐氏があり明智家がなければならない。
それは、天下人 明智光秀ということではない。
朝廷を中心とし、幕府が政治を行って統治する世の名を目指すためには、織田信長の天下布武のやり方ではいつまでたっても、戦が終わらないと考えたのだと思います。
おそらく、細川忠興(娘 ガラシャの嫁ぎ先)を担ぎだし、明智がそのバックアップを行い政治をコントロールする。そんな社会を描いていたのではないかと思います。
信長に取り入り、利用し、信用させ、政権交代のチャンスをうかがっていたのは間違いないと思います。
ただ、謀反の後の戦後処理計画がずさんであったことが残念であったのと、秀吉という傑物が光秀の理想を打ち砕いたということではないでしょうか。
ウィキペディアにはこう書かれています。
“ 在野史家・非専門家による「真相解明」と研究史上の評価
本能寺の変は当時最大の権力者であった信長が死亡し、時代の大きな転換点となったにもかかわらず、信長を討った光秀がその動機を明らかにした史料はなく、また光秀の重臣も短期間でほとんど討たれてしまったため、その動機が明らかにされることはなかった。
更に光秀がおくった手紙等も後難を恐れてほとんど隠蔽されてしまったため、本能寺の変の動機を示す資料は極めて限定されている。
しかしこれは裏返せば、個人の推理や憶測といった想像を働かせる余地が大きいということであり、中世史研究家ではない「素人」でも参入しやすい。
このため在野の研究家のみならず、小説家・ライターといった多くの人々が自説を展開してきた。
呉座勇一はこれほど多くの説が乱立している日本史上の陰謀は他にないと評している。
しかし日本中世史研究においてはあまり重視されたテーマではなく、日本中世史を専門とする大学教授が本能寺の変を主題とした単著は極めて少ない。
本能寺の変の歴史的意義としては信長が死んだことと秀吉が台頭したことであり、光秀の動機が何であれ、黒幕がいたとしても後世の歴史に何の影響も与えておらず、光秀の動機や黒幕を探る議論は「キワモノ」であると評価されている。”
と・・・。
どうやら、私がこのブログをあげてみなさんに見てもらうことは「キワモノ」を扱ってるようです。
私のような歴史に興味を持ちあれこれ勉強をしているような素人にすれば、いろんな推理や憶測ができるから面白い題材であるということか?
以後6か月で11回、今回で12回目になりましたが、ここまで来て” しまった “と思いました。
というのも、表記のことをいろいろ調べてみると、なんとその説がこんなにあるとは・・・。
怨恨説から野望説、恐怖心説などなどウィキペディアにおいては57もの説があるんですね。
これをひとつひとつ勉強し、ブログで説明するのはかなり難しいと感じました。
その必要もないしね。
そこで、その57の説についてはウィキペディアを見ていただければそれで良いかなと考えます。
<ウィキペディア(Wikipedia)の「本能寺の変」で入力して下さい。>
ただ、それでだけでは、あまりにも手抜きブログであり、来年の大河ドラマの参考にならず、また私の思うところも書けないまま、なんとも間の抜けた終わり方になりますので、
二三の興味ある記事を勉強しましたのでその内容についてご紹介し、最後に私の思う所を書かせていただきます。
四国征伐回避説
信長の四国征伐を回避するために謀反を起こしたとする説です。
平成26年に発見された長宗我部元親から斎藤利三に宛てた書状がこの説を裏付けているそうです。
この書状は、信長に対して、元親が土佐国・阿波2郡のみの領有と上洛に応じるという内容です。
しかし、信長は長宗我部元親の四国領有を認めていたのに、その約束を翻し、四国攻めの準備をしていました。
もし、この四国攻めが実行されると、秀吉と三好笑岩(康長)(阿波の国主)の勝利になる。(当時、光秀-元親ラインに対して秀吉-康長ラインという図式があった。)
また、元親に対して光秀は面目が立たなくなる。
ということは、光秀も失脚させられる可能性が高くなる。
ということで、謀反に踏み切ったというものです。
共謀説(土岐明智家滅亡阻止説)
明智光秀の子の於隺丸(おづるまる)の子孫であると称しておられる明智憲三郎氏の説です。
※ 明智光秀 生存説(天海=光秀説/天海=秀満説)を唱えた明智滝朗氏は憲三郎氏のおじいさんです。
光秀は、信長の次なる野望、唐への侵攻を知っていました。
これが実行されると、自分はともかく明智一族はこの侵攻に駆り出され、それは一族の滅亡に繋がると危惧していました。
そんなとき、信長は家康を安土に呼び武田討伐の労をねぎらいました。
このとき、信長は光秀に家康を討たせて、徳川領を我が物にしようとしました。
光秀は、この計画を逆手に取り家康と結託し謀反を起こした。というものです。
上記の2説についても、いろんな意見があり、確たるものでは無いようです。
次に、これには私も「なるほど!」とうなりました(笑)
某ウェブサイトのブログにあった説です。
秀吉は中国の毛利氏と対峙していた時、四国の長宗我部氏も信長から討伐せよと命じられていました。
そこで、援軍を信長に乞うたところ、織田信孝を大将に丹羽長秀以下14,000の軍勢を応援に向かわせようとしていました。
信長は、光秀にも四国討伐の手助けをするように命令しましたが、長宗我部と親しくしている光秀にとってそれは出来ない相談でした。
長宗我部元親とは、信長を討つ約束までしている。もし元親を裏切って四国討伐に加担しようとすれば、元親は信長に光秀謀反の心有りとばらされてしまう。
したがって、どうしても四国討伐を阻止する必要があったわけです。
そこで、光秀はイエズス会のルイス・フロイスを動かそうとしたのです。
キリスト教布教のために信長と結託していたイエズス会ですが、なかなか信長は全面的な布教活動に協力してくれなかった。
徐々に、その関係は崩れていき、信長以外のスポンサーを見つけようとフロイスは思っていました。
光秀は、フロイスに「信長を討って、大伴宗麟を天下人にすることができるが・・・」
大伴宗麟は周囲の反対を押し切ってキリスト教に改宗した人で、ルイスは彼ならイエズス会の布教活動も進められると判断しました。
しかし、光秀にはその場での返事を保留し、大伴氏に相談したのです。
大伴宗麟は、光秀がそんな大それたことを考えていることに懸念を持ち、協力関係にあった秀吉にその事実を相談したのです。
秀吉はルイスに、「光秀の話には乗らず、お館様に光秀のたくらみを伝えよ!」とは言わなかったのです。
秀吉という人物も、立身出世を狙っていた狡猾な人間です。
彼はルイスに「大友宗麟は明智殿に協力する。だから明智殿も必ず信長公を誅してほしい」と光秀に言いなさいと・・・。
これが、光秀謀反の経緯であるという説です。
で、私の考えですが、
柴田勝家や佐久間など従来の家臣は織田家があって、自分がある。
織田家が繁栄することが、自らの出世に繋がるという忠誠心があります。
しかし、秀吉も家康も光秀も織田家譜代の家臣ではありません。
秀吉は貧乏な百姓上がりであるがゆえに、出世欲は人一倍強かったと思います。
家康は三河の松平家の嫡男として生まれ、いずれはお家再興し徳川の世を築きたいという気持ちはあったと思います。
光秀も、美濃は土岐氏という名家の出身である以上、いずれは天下にその名を轟かせたいと思っていたと思います。
また、光秀は斎藤道三に仕えており、道三が一油売りの商人から美濃国を下剋上により奪い取った生きざまを見てきています。
したがって、光秀は突発的にとか、怨恨でとか、誰かと共謀してとか、黒幕がいたとか、そういう次元の話では無いと思います。
理想とする国造り・・・それは応仁の乱以降、乱れに乱れた日本国の再建。戦に明け暮れる社会を終わらせる。そうした国造りの中心に土岐氏があり明智家がなければならない。
それは、天下人 明智光秀ということではない。
朝廷を中心とし、幕府が政治を行って統治する世の名を目指すためには、織田信長の天下布武のやり方ではいつまでたっても、戦が終わらないと考えたのだと思います。
おそらく、細川忠興(娘 ガラシャの嫁ぎ先)を担ぎだし、明智がそのバックアップを行い政治をコントロールする。そんな社会を描いていたのではないかと思います。
信長に取り入り、利用し、信用させ、政権交代のチャンスをうかがっていたのは間違いないと思います。
ただ、謀反の後の戦後処理計画がずさんであったことが残念であったのと、秀吉という傑物が光秀の理想を打ち砕いたということではないでしょうか。
ウィキペディアにはこう書かれています。
“ 在野史家・非専門家による「真相解明」と研究史上の評価
本能寺の変は当時最大の権力者であった信長が死亡し、時代の大きな転換点となったにもかかわらず、信長を討った光秀がその動機を明らかにした史料はなく、また光秀の重臣も短期間でほとんど討たれてしまったため、その動機が明らかにされることはなかった。
更に光秀がおくった手紙等も後難を恐れてほとんど隠蔽されてしまったため、本能寺の変の動機を示す資料は極めて限定されている。
しかしこれは裏返せば、個人の推理や憶測といった想像を働かせる余地が大きいということであり、中世史研究家ではない「素人」でも参入しやすい。
このため在野の研究家のみならず、小説家・ライターといった多くの人々が自説を展開してきた。
呉座勇一はこれほど多くの説が乱立している日本史上の陰謀は他にないと評している。
しかし日本中世史研究においてはあまり重視されたテーマではなく、日本中世史を専門とする大学教授が本能寺の変を主題とした単著は極めて少ない。
本能寺の変の歴史的意義としては信長が死んだことと秀吉が台頭したことであり、光秀の動機が何であれ、黒幕がいたとしても後世の歴史に何の影響も与えておらず、光秀の動機や黒幕を探る議論は「キワモノ」であると評価されている。”
と・・・。
どうやら、私がこのブログをあげてみなさんに見てもらうことは「キワモノ」を扱ってるようです。
私のような歴史に興味を持ちあれこれ勉強をしているような素人にすれば、いろんな推理や憶測ができるから面白い題材であるということか?
閲覧(3108)
| カテゴリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
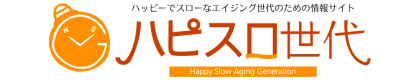





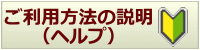
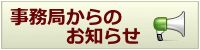

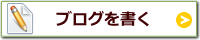
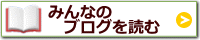
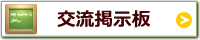
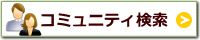
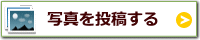
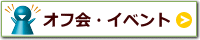
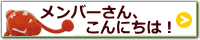
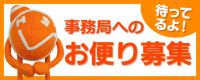
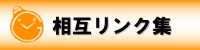


 前の日記
前の日記



 」てわからなくなりますよ。
」てわからなくなりますよ。